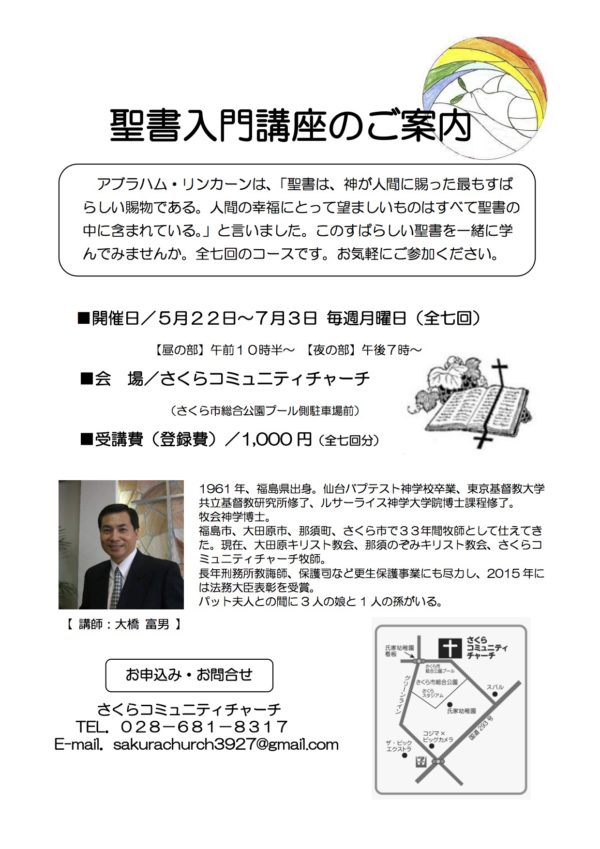投稿日: 2018/04/28 投稿者: Tomio Ohashi
きょうは「返さなければならない負債」というタイトルでお話したいと思います。先週は、まだ一度も会ったことのないローマのクリスチャンたちに自分を紹介するにあたり、パウロが「神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリスト・イエスのしもべパウロ」と紹介したことを学びました。パウロは、自分がこの福音のために選び分けられた者であるという強い自覚と使命感がありました。このような使命感があったからこそ、彼は本気で福音のために献身することができたのです。
さて、きょうのところは先週に引き続きこの手紙全体の導入の部分ですが、きょうのところでパウロは、自分がなぜローマに行きたかったのか、その理由を述べています。11節を見るとここには、「私があなたがたに会いたいと切に望むのは」とか、13節にも、「何度もあなたがたのところに行こうとした」とか、15節のところにも、「ですから、私としては、ローマにいるあなたがたにも、ぜひ福音を伝えたいのです。」とあります。いったいパウロはなぜそんなにローマに行きたかったのでしょうか。きょうはその理由を三つのポイントでお話したいと思います。
第一のことは、それは彼らの信仰が全世界に言い伝えられていたからです。第二のことは、互いの信仰によって、ともに励ましを受けたいと願っていたからです。そして第三のことは、それが返さなければならない負債であると思っていたからです。
Ⅰ.全世界に言い伝えられている信仰(8)
それではまず8節をご覧ください。パウロがローマに行きたかったのは、ローマのクリスチャンたちの信仰が全世界に伝えられていたからです。
「まず第一に、あなたがたすべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それは、あなたがたの信仰が全世界に言い伝えられているからです。」
パウロはまずローマのクリスチャンたちのことで、神に感謝しています。それは、彼らの信仰が全世界に言い伝えられていたからです。全世界に言い伝えられていた信仰とはどのような信仰だったのでしょうか。これと同じようなことがテサロニケ人への手紙の中にも記されてありますのでご覧いただきたいと思います。Iテサロニケ1章8節です。
「主のことばが、あなたがたのところから出てマケドニヤとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなたがたの信仰はあらゆる所に伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。」
ここで言われている信仰とは、彼らの聖い生活とか、愛に満ちた生活ということではなく、神に対する信仰です。それはどのような信仰かというと、キリスト信仰のことです。キリストによって罪から救われ、新しい人生に導かれた者として、そのキリストとともに生きる信仰のことなのです。パウロはその信仰をガラテヤ人への手紙の中で次のように告白しました。
「私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。」(ガラテヤ2:20)
この信仰です。ローマのクリスチャンたちは、この信仰に生きていました。皇帝を神としてあがめるローマ帝国の首都にあって、この信仰に生きることはどんなに大変なことだったでしょう。けれども彼らはこの信仰に生き、キリストを立派にあかししていたのです。それはローマ全体から見たならほんの一握りの人々であったかもしれません。しかし、彼らのそうした不撓不屈(ふとうふくつ:どんな困難に出あっても心がくじけないこと)の信仰は、ほかの地にいるクリスチャンにとって大きな励ましであり、また良い模範となりました。パウロはこのローマのクリスチャンたちがそのような信仰を持つようになったことを神に感謝したのです。
それは昔から信仰に生きた人たちに共通して見られるものです。たとえば、ダニエル書にはシャデラク、メシャク、アベデ・ネゴという三人の少年たちが登場しますが、彼らはバビロンの王ネブカデネザル王から、もろもろの楽器の音を聞く時には、ひれ伏して、彼が造った像を拝むようにと命じられても、決して拝もうとしませんでした。それによってたとえ火の燃える炉の中に投げ込まれてもです。その時彼らは王に次のように答えました。
「もし、そうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ。神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが立てた金の像を拝むこともしません。」(ダニエル3:17,18)
「しかし、もしそうでなくても・・」というのがすばらしいと思います。私の神は、私の信じている神は、そのような火の燃える炉から救い出すことができますが、たとえそうでなくても、決して金の像を拝むようなことはしない、そう言ったのです。彼らは自分たちのいのちに優先する信仰として、どんな状況にあっても揺るがない、ただ神だけに拠り頼む、そのような信仰を持っていたのです。
皆さんはいかがですか。皆さんには、「もし、そうでなくても」という信仰がおありでしょうか。もし自分の思うように進まなくても、もし自分の願いが叶わなくても、もし、このことによって苦難を受けるようなことがあっても、それでも私はこの神に拠り頼むという信仰がおありでしょうか。
スウェーデンの宣教師デヴィッド・フラッドという人の伝記を読みました。彼は福音を伝えるために、妻と2歳の息子とともに1921年、アフリカのコンゴに向かいました。飢餓と病気、敵対的な部族の人々の中で困難な働きを続けました。宣教の唯一の実は、一人の幼い少年だけでした。彼はそこで毎週日曜日にその幼い少年に聖書を教えました。そんな中、妻が娘を出産して七日目に世を去ってしまったのです。度重なる困難に疲れ果てたフラッドは、妻まで失ったことで自暴自棄に陥りました。神に失望し、殉教まで覚悟していた信仰を捨てて、現地の宣教本部に娘を預け、息子だけを連れて本国に戻ったのです。
その後、73歳になった彼は、40年ぶりにはじめて会った娘から驚くべき事実を聞くのです。娘は、父に会いに来る途中、ロンドンのある集会で黒人の牧師に会ったのですが、それがあのコンゴの少年だったのです。その少年は立派に成長して牧師になり、福音の不毛地と言われたコンゴで神に仕える器となったのです。そして今では32カ国に宣教師を送り、11万人ものクリスチャンのいる教会の牧師となりました。父の献身と母の殉教によって、コンゴに新しいいのちがたくさん生まれていたのです。娘が「お父さんのしたことは決して無駄ではなかったのです」という言葉に、フラッドは涙して悔い改めたのでした。
主のために努力したのに、結果が思ったとおりでないとき、私たちは失望します。しかし、たとえそうでなくても、それでもただ神に従うという信仰が重要です。まことの神を信じるなら、あらゆる結果を感謝して受け入れることができるようになるのです。
実にローマのクリスチャンたちにはそのような信仰がありました。この世のこと、この地上のものを求めてやまないこの世の人たちとは違って、神のこと、永遠のことを求めて生きていたのです。そういう原理に生きていました。信仰が生きていたのです。ローマのクリスチャンたちはパウロによって信仰に導かれたわけではありませんでしたが、彼らがそのような信仰を持って歩んでいるというあかしを聞き、そのように導かれた神に感謝をささげると同時に、そういう彼らに何とかして会いたいと願っていたのです。
Ⅱ.ともに励ましを受けるため(9-12)
パウロがローマに行きたかったもう一つの理由は、ともに励ましを受けたかったからです。9~12節をご覧ください。
「私が御子の福音を宣べ伝えつつ霊をもって仕えている神があかししてくださることですが、私はあなたがたのことを思わぬ時はなく、いつも祈りのたびごとに、神のみこころによって、何とかして、今度はついに道が開かれて、あなたがたのところに行けるようにと願っています。私があなたがたに会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなたがたに分けて、あなたがたを強くしたいからです。というよりも、あなたがたの間にいて、あなたがたと私との互いの信仰によって、ともに励ましを受けたいのです。」
まだ一度も会ったことのないローマのクリスチャンたちではありますが、パウロはいつも彼らのことを思っていました。どのように?祈りによってです。祈りによって彼は、いつも彼らのことを思い、神のみこころによって、何とかして道が開かれて、彼らのところに行けるようにと願っていたのです。いったいなぜパウロはそんなにも彼らのところに行くことを切望していたのでしょうか。それは11、12節にあるように、御霊の賜物をいくらかでも彼らに分け与えて、彼らの信仰を強くしたかったからです。なぜ彼らの信仰を強くしたかったのでしょう。伝道者、牧師であればそれは当然のことです。そのために自分が用いられるのであれば、喜んでそうしたいと思うのが普通です。しかしパウロの場合はただそのような理由だけではありませんでした。この手紙の終わりの方、15章を見ていただくとわかりますが、どうも彼はもっと遠く西方に、イスパニヤ、今のスペインですね、そこまで福音を宣べ伝えたいと願っていたようです。その宣教の拠点としてこのローマ教会に立ってほしかった。そのために必要だったことは、彼らが福音によってその信仰がしっかりと立っているということでした。なぜなら、福音に力があるからです。福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって神の力です。その福音にしっかりととどまっていてほしかった。だからこの手紙を書いたのです。本当なら、ローマまで行って直に会い、顔と顔とを合わせて教えるのに越したことはありません。しかし今はそれができないので、こうやって手紙を書いて彼らを強めようとしているのです。
しかし、パウロがローマに行きたかったのは、そのように彼に与えられた御霊の賜物を分け与えて、彼らを強くするためだけではありませんでした。12節、「というよりも、彼らの間にいて、互いの信仰によって、ともに励ましを受けたかったからなのです。」
皆さん、私たちクリスチャンには、それぞれ御霊の賜物が与えられています。この御霊の賜物についてパウロは、ローマ書12章3~8節のところで次のように言っています。
「私は、自分に与えられた恵みによって、あなたがたひとりひとりに言います。だれでも、思うべき限度を越えて思い上がってはいけません。いや、むしろ、神がおのおのに分け与えてくださった信仰の量りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つのからだには多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。」
一つのからだには器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとりが互いに器官なのです。ですから、その与えられた御霊の賜物を、主に喜ばれるように、ほかの人々のために用いていかなければなりません。パウロには預言の賜物があったでしょう。教える賜物も、勧める賜物も、指導する賜物もあったかもしれません。かといって、彼がオールマイティーであったかというとそうではありません。おそらく、人を励ますという賜物は弱かったのではないかと思います。それはあのバルナバとの激しい反目をみるとわかります。彼らが第二次伝道旅行に出かけて行こうとした時、マルコを連れて行くかどうかで話し合った時、彼らの間に激しい反目が起こりました。先の伝道で途中から戻った者など伝道者としてふさわしくないと主張したパウロと、いや、人はみな弱さがあって完全ということはないんだから、そういう人をも受け入れていく必要があると主張したバルナバとの間に、激しい口論が生じたのです。結局、マルコを連れて行ったのはバルナバでした。パウロはなかなか受け入れることができなかった。もちろん、後でパウロはそのマルコさえも心から許し、受け入れましたが・・・。どちらが正しかったのかというよりも、人にはいろいろな性格や賜物、考え方があるので、そのような違いが生じてくるのです。しかし、それはやはりパウロの度量のなさというか、弱さからくる限界でした。やはり人を励ますという点ではバルナバの方が優れていました。とは言ってもみながバルナバだったらいいのかというとそうではありません。バルナバのような人がいて、パウロのような人がいて、それぞれに与えられた賜物を用いることによってともに励ましを受けることが大切なのです。神様は、そのために必要な人材してそれぞれを教会に置いてくださったのです。ですから、それぞれに与えられた賜物を用いて、互いに主に仕え合わなければなりません。そのためには、自分に与えられている霊的賜物を、ほかの兄弟姉妹に喜んで分け与えようという愛と、自分もまた教えられ、祝福を受ける必要があるということを十分認識し、そうした欠けを補いたいという謙虚さが必要です。この両者のあるところにクリスチャンの交わりがあり、それは大きな恵みをもたらしていくのです。
19世紀のアメリカの偉大なリバイバリスト、D・L・ムーディの周りには、彼を支えた多くの人たちがいました。賛美の奉仕をしたのはサンキという人ですが、この人は生涯ムーディとともに働きました。ムーディーが行く先々で、まずサンキが賛美して人々の心を開き、熱くしました。ムーディとサンキの関係は、まさに同労者の関係でした。またムーディはサンキだけでなく、R・A・トーレイという神学者もいつも連れて行きました。この人は、それほど説教がすぐれていたわけではありませんでしたが、しっかりとした神学的背景を持っていたので、靴屋から献身し、それほど教育を受けられなかったムーディにとっては、そうした神学的知識で理路整然に文章をまとめ、説教の原稿を作ったり、バイブルスタディの教材を作ったりしてもらえたことは、大きな助けでした。
パウロは、「あなたがたと私との互いの信仰によって、ともに励ましを受けたいのです。」と言いました。私たちはこのような励ましをみな必要としているのです。お互いに心を開き、このような交わりを持つように励みたいものです。
Ⅲ.返さなければならない負債(13-15)
パウロがどうしてもローマに行きたかった第三の理由は、それが返さなければならない負債だったからです。13~15節までをご覧ください。ここでパウロは、
「兄弟たち。ぜひ知っておいていただきたい。私はあなたがたの中でも、ほかの国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って、何度もあなたがたのところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私は、ギリシヤ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから、私としては、ローマにいるあなたがたにも、ぜひ福音を伝えたいのです。」
と言っています。パウロは、何度もローマに行こうとしましたが、なかなかそれを果たすことができませんでした。なお妨げられていたのです。パウロがこの手紙を書いたのは、第三次伝道旅行でエペソに3年間滞在したのち、マケドニヤ、アカヤを訪れた時でした。コリントに三ヶ月間滞在していた時でした。コリントといったらローマまでひとっ飛びです。もう少しで行けるというところまで来ていましたが、マケドニヤからの献金を携えてエルサレムに行かなければなりませんでした。今なお妨げられているのです。しょうがないから彼はそこで手紙を書いて、隣町ケンクレヤの女執事フィベに託して手紙を送り届けたのです。それにしてもなぜパウロはローマに行くことをそれほど願ったのでしょうか。その理由は14節にあります。
「私は、ギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。」
パウロはそれを「返さなければならない負債」だと思っていました。「負債」とは、辞書で調べてみると、「他から金銭や物品を借りて、返済の義務を負うこと。また、その借りたもの。借金。債務。」とあります。それは義務なのです。ローマ人やギリシャ人に対して実際に負債を負っていたというのではなく、その人たちに返さなければならない負債を「神に対して」負っていたという意味です。つまり、神がそのことを要求しておられるとパウロは考えていたのです。
パウロはその使命を負債のように感じていました。負債を負っている人なら、あるいはかつて負ったことのある人ならパウロの気持ちがよくわかるのではないでしょうか。それが常に重荷となってのし掛かってきます。「返さなければならない」というプレッシャーとなって日々全身に重く感じるのです。パウロがローマに行って福音を伝えたいと思ったのは、それは神から与えられた大きな恵みのゆえに、どうしても返さなければならない負債だったのです。
ここに私たちクリスチャンのあるべき姿がよく表されているのではないかと思うのです。つまり、私たちは自分が何をしたいのか、どこに行きたいのかといった個人的な思いからあれをしよう、これをしようと選択して生きているのではなく、神が何をしてほしいのかを知り、それを行っていくことが大切であるということです。そういう基準で生きる(行動する、選択する)ことです。
現代の人は「こうしなければならない」ということを極端に嫌います。代わりに「権利、権利」と、権利ばかりを主張するのです。しかし、すべての状態が自分の都合に合致しなければ喜べないというのは自己中心的であり、幼い人で、その心を変えなければ、いつまでたっても成長はありません。すべての事が自分の思うとおりにはいくとは限らないからです。神から与えられた仕事を、神のために、神のお喜びのためにやるという心を持つ時に、大人のような立派なクリスチャンになることができるのです。パウロはそうでした。彼はいつも神のために何が一番良いことなのかを求めて生きました。たとえばコリント第一の手紙9章には、彼は飲み食いする権利、妻を連れて歩く権利、まあ、これは結婚のことですが、それから働きのために報酬を受ける権利があるが、そのような権利を一つも用いなかったと告白しています。なぜでしょうか?より多くの人を獲得するためです。
「私はだれに対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。」(Iコリント9:19)
彼はすべてのことを福音のためにしました。パウロは信仰によって、福音のために何が一番良いのかという選択をしました。それが霊的大人の考え方です。そのように考えるなら、このような義務は祝福であることがわかります。また、そのような務めが私たちに与えられているということは、神がそのような者として私たちを認め期待しておられるということの裏返しでもあるわけですから、本当に感謝なことなのです。数年前のペットの流行は「ホーランドロップ」といううさぎだそうですが、どんなにホーランドロップが癒し系のかわいいうさぎだからといって、そのうさぎに家中を掃除することを期待するでしょうか。しないです。そのようなものとして認めていないからです。家にはかわいいフェレットがいますが、このフェレットに何らかの責任を与えたりするでしょうか。「フェレットちゃん、きょうはおとなしくお留守番しているのよ」なんて言いません。そのようなことを期待していないからです。カエルにお買い物を頼みますか?「頼むから美味しい食べ物を買ってきてくれませんか」なんて・・。しません。できないからです。そんなこと言ったら、「もうカ~エル!」なんて言われるでしょう。そのように責任を与えるということは、それができると認めているからであって、できなかったら与えません。神様は私たちにそのような務めを与えてくださったというのは、そのような者として私たちを見ておられるからなのです。もし私たちが神から与えられた義務と責任をすばらしいものとしてとらえることができれば、一人の人間として、クリスチャンとして、必ず成長していくことになるのです。
パウロは、「私は、ギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています」と言いました。「ギリシャ人にも未開人にも」とか、「知識のある人にも知識のない人にも」というのは、世界中のあらゆる人々にという意味です。パウロの関心は、世界中のどこにおいても、この福音を宣べ伝えることでした。それが自分に与えられた使命であり、どうしてもしなければならない負債だと考えたのです。それはパウロだけではありません。私たちも同じです。私たちも同じ負債を負っているのです。私たちはそれほど大きな神の恵みを受けたからです。神の御子をこの世に与え、十字架につけて死なせ、三日目によみがえらせることによって、この方を信じる者はだれでも救われるという道を開いてくださったのです。そのおかげで、私たちはたましいの救いを得ることができました。何と大きな恵みでしょうか。私たちはそれほどの恵みを受けたのならば、その恵みを何らかの形でお返ししたいと思うのが当然ではないでしょうか。パウロはその神の大きな恵みのゆえに、この福音宣教を、どうしても返さなければならない負債だと感じていたのです。それは私たちも同じです。私たちも恵みを受けたのです。ですから、これがどうしても返さなければならない負債、いや、それこそ私たちの願いであると受け止めるられるなら、神の国がますます大きく前進していくだけでなく、私たち自身の祝福ともなるのです。
ですからパウロは何とかしてローマに行きたかった。ローマにいる彼らにも、ぜひ福音を伝えたかったのです。私たちもパウロのような情熱をもって、神のみこころに生きることを求めていきたいものです。
メッセージへ戻る