聖書箇所:エレミヤ書39章1~18節(旧約P1366、エレミヤ書講解説教69回目)
タイトル:「主に信頼する者は守られる」
きょうから、エレミヤ書の講解説教に戻ります。きょうは39章全体から、「主に信頼する者は守られる」というタイトルでお話します。これまでエレミヤを通して何度も語られてきたエルサレム陥落の預言が、ここに実現します。これは旧約聖書を理解する上でとても大切な鍵になる出来事なのでぜひとも覚えておいていただきたいのですが、前586年のことです。しかし、その中にあっても救われた人たちがいます。それはこのエレミヤであったり、クシュ人エベデ・メレクといった人たちです。どうして彼らは救われたのでしょうか。それは彼らが主に信頼したからです。きょうの箇所の17節と18節にこうあります。
「17 しかしその日、わたしはあなたを救い出す──主のことば──。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。18 わたしは必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたのいのちは戦勝品としてあなたのものになる。あなたがわたしに信頼したからだ──主のことば。』」
皆さん、主に信頼する者は守られます。主はそのような人を必ず助け出してくださるのです。きょうは、このことについて三つのことをお話します。第一に、エルサレム攻め取られた次第です。エルサレムはどのように陥落したのでしょうか。それは主が語られた通りでした。主が語られたことは必ず実現するのです。第二のことは、そのような中でもエレミヤは解放されました。どうしてでしょうか。それはエレミヤが語ったとおりになったことを、異教徒のバビロンの王ネブカドネツァルや親衛隊の長ネブザルアダンが認めたからです。つまり、彼らはそれが神の御業であることを認めたのです。だから、神が語られたことは必ず実現すると信じて、神に信頼しなければなりません。第三のことは、クシュ人エベデ・メレクの救いです。彼は異邦人でありながどうして救い出されたのでしょうか。それは、彼が主に信頼していたからです。主に信頼する者は守られるのです。
Ⅰ.エルサレム陥落(1-10)
まず、1~10節をご覧ください。1~3節をお読みします。
「1 ユダの王ゼデキヤの第九年、第十の月に、バビロンの王ネブカドネツァルは、その全軍勢を率いてエルサレムに攻めて来て、これを包囲した。2 ゼデキヤの第十一年、第四の月の九日に、都は破られ、3 バビロンの王のすべての首長たちが入って来て、中央の門のところに座を占めた。すなわち、ネルガル・サル・エツェル、サムガル・ネブ、ラブ・サリスのサル・セキム、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。」
前の章、38章の最後の節には、「エルサレムが攻め取られた次第は次のとおりである」とありますが、ここにはエルサレムが攻め取られた次第、すなわち、エルサレムがどのように陥落したのかが記されてあります。
ユダの王ゼデキヤの第九年とはユダヤの暦ですが、これは現代の暦で言うと前588年のことです。その年の第十の月に、バビロンの王ネブカドネツァルは、その全軍勢を率いてエルサレムに攻め入り、これを包囲しました。そしてゼデキヤの治世の第十一年の第四の月、これは現代の暦で言うと前586年7月となります。ですから、実に2年半もの間、エルサレムはバビロンによって包囲されていたわけですが、ついにその城壁が破られる時が来たのです。その時、バビロンの王のすべての首長たちがエルサレムに入って来て、中央の門のところに座を閉めました。これは、軍の総司令本部を置いたということです。エルサレム陥落です。
それを見たユダの王ゼデキヤはどうしたでしょうか。4~7節までをご覧ください。
「4 ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は、彼らを見ると逃げ、夜の間に、王の園の道伝いにある、二重の城壁の間の門を通って都を出て、アラバへの道に出た。5 カルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王ネブカドネツァルのもとに連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。6 バビロンの王はリブラで、ゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺し、ユダのおもだった人たちもみな虐殺した。7 さらに、バビロンの王はゼデキヤの目をつぶし、バビロンに連れて行くため、彼に青銅の足かせをはめた。」
それを見たゼデキヤとすべての戦士は逃げ、夜の暗やみに乗じてエルサレムを脱出し、アラバへの道に出ました。アラバは、ヨルダン川沿いの南北に伸びている低地です。すなわち、彼らはエリコの方面に逃げたわけです。しかし、そのエリコの草原でバビロンの追跡軍に追いつかれると、捕らえられてハマテの地リブラにいるバビロンの王ネブカドネツァルのもとに連れて行かれました。リブラはエルサレムの北約350キロのところにあります。ゼデキヤはそこでネブカドネツァルと対面することになったのです。
するとバビロンの王は、ゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺し、ユダの首長たちもみな虐殺しました。しかし、ゼデキヤは剣で殺されることはありませんでした。彼は両目をえぐり取られ、青銅の足かせにつながれて、バビロンに連れて行かれることになりました。ゼデキヤがその目で最後に見たのは、自分の息子たちが殺される光景でした。なんと悲惨な人生でしょうか。このようにして、エルサレムは陥落し、城壁は破られ、町は火で焼かれ、そのおもな住民は、9節にあるように、バビロンへ捕囚の民として連れて行かれたのです。
一方、何も持たない貧しい民の一部はどうなったかというと、10節にあるように、ユダの地に残され、ぶどう畑と畑地が与えられました。どうして彼らにぶどう畑や畑地が与えられたのかはわかりません。恐らくネブカドネツァル王は、それまで冷遇され、みじめな生活を強いられていたユダの貧しい人々が、悪利をむさぼり土地を自分たちの思うように使っていた身分の高い人々に反感を持っていたことを知っていたのでしょう。支配下に置かれた地域を有効に治めるために、彼らにぶどう畑や畑の所有権を与えることにしたのです。
問題は、こうしたエルサレムが陥落した一連の出来事は、これを読む読者に何を伝えようとしているのかということです。それは、神が語られたことは必ず実現するということです。それは、時にはのろいのようにしか見えないかもしれませんが、それが良いことであれ悪いことであれ、時が来ると必ず実現するのです。ここに記されてあることはすべて、預言者エレミヤによって預言されていたことです。それがここに実現したのです。たとえば、エルサレムはバビロンの王の手に渡され、火で焼かれることや、ゼデキヤは必ず捉えられて、彼の手、すなわちバビロンの王の手に渡されるということ、そこで彼はバビロンの王の目を見、王の口と語るということ、しかし彼は剣で死ぬことはなく、バビロンに連れて行かれることになるということについては、エレミヤが預言していたことでした。エレミヤ34章2~5節をご覧ください。
「34:2 「イスラエルの神、【主】はこう言う。行って、ユダの王ゼデキヤに告げよ。『【主】はこう言われる。見よ、わたしはこの都をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼く。34:3 あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて、彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。34:4 ただ、【主】のことばを聞け、ユダの王ゼデキヤよ。【主】はあなたについてこう言われる。あなたは剣で死ぬことはない。34:5 あなたは平安のうちに死ぬ。人々は、あなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために埋葬の香をたいたように、あなたのためにも香をたき、ああ主君よ、と言ってあなたを悼む。このことを語るのはわたしだ──【主】のことば。』」
これはエレミヤが以前預言していたことです。この預言のとおりに、エルサレムは火で焼かれ、ゼデキヤ王は捕らえられてバビロンの王の手に渡されました。そこで彼はバビロンの王の目を見、彼の口と語りました。しかし彼は剣で死ぬことはなく、バビロンに連れて行かれることになったのです。また9節に「親衛隊の長ネブザルアダンは、都に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、そのほかの残されていた民を、バビロンへ捕らえ移した。」とありますが、このこともエレミヤによって預言されていたことです。すなわち、これら一連の出来事は、預言者エレミヤによって預言されていたことがそのとおりに実現したということです。
エルサレムはどのように攻め取られたのでしょうか。すべてエレミヤによって語られていたとおりに、です。神が語られたことは必ず実現するのです。その時点では「どうかなあ」「そんなことはないだろう」と思うかもしれませんが、時が来ると、その通りであったことを知ることになります。
イスラエルを約束の地に導いた時のリーダーはモーセの従者ヨシュアでしたが、彼はその晩年、このように告白しました。
「23:14 見よ。今日、私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたがたは心を尽くし、いのちを尽くして、知りなさい。あなたがたの神、【主】があなたがたについて約束されたすべての良いことは、一つもたがわなかったことを。それらはみな、あなたがたのために実現し、一つもたがわなかった。23:15 あなたがたの神、【主】があなたがたに約束されたすべての良いことが、あなたがたに実現したように、【主】はまた、すべての悪いことをあなたがたにもたらし、ついには、あなたがたの神、【主】がお与えになったこの良い地からあなたがたを根絶やしにされる。23:16 主があなたがたに命じられた、あなたがたの神、【主】の契約を破り、行ってほかの神々に仕え、それらを拝むなら、【主】の怒りはあなたがたに対して燃え上がり、あなたがたは、主がお与えになったこの良い地から速やかに滅び失せる。」(ヨシュア21:14-16)
ヨシュアはその晩年、自分の生涯を振り返り、主が自分たちに約束されたことは、それが良い事であれ、悪いことであれ、一つもたがわずみな実現した、と告白しました。皆さん、主が約束されたことはみな実現します。たとえ今、何の変化もないようでも、時が来れば、神が語られたとおりに実現したことを知るようになるのです。
アメリカのミネソタ州にベイウィンド・クリスチャンチャーチという教会がありますが、その教会の牧師であるヘルマー・ヘッケル牧師の証を読んだことがあります。彼は、1958年にドイツからアメリカに移住した移民者です。彼はアメリカへの移住を果たすとすぐに路傍伝道で救われ、献身しました。その彼がドイツからアメリカにやって来た時のことを想起して、次のように言っています。
「1958年12月、私は輸送船ブトナー号に乗ってドイツからアメリカにやって来ました。ブレマーハーフェン港を出港し、北海を通って北大西洋に入りました。船は荒波にもまれ、来る日も来る日も、北を向いても南を向いても、東を向いても西を向いても、見えるのはと言えば水また水、聞こえるものと言えば船のエンジンだけという単調なうなり声だけでした。
しかし5日後に、劇的な変化がやって来ました。東と南に見えるのは海水だけでしたが、西には自由の女神像が朝日にきらめいていたのです。ようやくたどり着くことができたのです。」
彼は、ようやくたどり着くことができました。信仰によって歩むのもこれと同じです。私たちの置かれている状況は何の変化もないようですが、時が来れば、神が語られたことは必ず成就し、私たちは主のご計画のままに導かれてきたことを知るようになるのです。それは、これから先のことについても言えることです。聖書は世の終わりのことにどんなことが起こるかをはっきり語っています。であれば私たちはその神のことばを信じ、そのことばに従い、ただ神に信頼して、神に忠実に歩まなければなりません。たとえあなたの人生が拓かれていないように見えても、神は必ず語られたことを実現してくださいますから、ただみことばに信頼して歩ませていただきたいと思うのです。
Ⅱ.エレミヤの解放 (11-14)
次に、11~14節をご覧ください。
「11 バビロンの王ネブカドネツァルは、エレミヤについて、親衛隊の長ネブザルアダンを通して次のように命じた。12 「彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語るとおりに、彼を扱え。」13 こうして、親衛隊の長ネブザルアダンと、ラブ・サリスのネブシャズバンと、ラブ・マグのネルガル・サル・エツェルと、バビロンの王のすべての高官たちは、14 人を遣わして、エレミヤを監視の庭から連れ出し、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに渡して、家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだ。」
ここにはエレミヤの処遇について、バビロンの王ネブカドネツァルが親衛隊の長ネブザルアダンに命じたことが記されてあります。その内容は、エレミヤを連れ出し、目をかけてやれということでした。目をかけてやるとは、かわいがって面倒をみるとか、ひいきにするということです。バビロンの王はエレミヤをかわいがって面倒を見るようにと命じたのです。悪いことは何もするなと。ただ彼が語るとおりに、彼を扱うようにと。こうして親衛隊長のネブザルアダンとバビロンの王の高官たちは、人を遣わしてエレミヤを監視の庭から連れ出し、エルサレムの総督に任じられていたシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤの家に連れて行かせました。そこは特別な保護の下で安全に過ごすことができる場所だったからです。これこそ神が備えられた助けだったのです。いったいなぜネブカドネツァルはこのように命じたのでしょうか。
恐らくエレミヤのことを誰かから聞いていたのでしょう。彼がどんなことを語っていたのかを。つまり、バビロンに降伏することこそが神のみこころであり、ユダの民が生きる道であるということを。彼はエレミヤが忠実な神の預言者であるとか、バビロンにとって有益な人物だからという理由で目をかけてやれと言ったのではありません。ただエレミヤが語っていたとおりになったのを見て驚いたのです。それは40章2~4節を見てもわかります。ここでは、そのネブカドネツァルの親衛隊の長ネブザルアダンがエレミヤを釈放する時にこのように言ったことが記されてあります。
「40:2 親衛隊の長はエレミヤを連れ出して、彼に言った。「あなたの神、【主】は、この場所にこのわざわいを下すと語られた。40:3 そして【主】はこれを下し、語ったとおりに行われた。あなたがたが【主】の前に罪ある者となり、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなたがたに下ったのだ。40:4 そこで今、見よ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いて、あなたを釈放する。もし私とともにバビロンへ行くのがよいと思うなら、行きなさい。私があなたの世話をしよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないなら、やめなさい。見なさい。全地はあなたの前に広がっている。あなたが行ってよいと思う、気に入ったところへ行きなさい。」」
ここで親衛隊の長ネブザルアダンはエレミヤに、主はこの場所にわざわいを下すと語られたとおりに行われた、と言っています。つまりエレミヤが語ったとおりに、ユダの民が神の声に聞き従わず、神の前に罪ある者となったので、エルサレムが陥落した。だから、エレミヤを釈放すると言ったのです。彼は異教徒でありながらも、イスラエルの神、主がエレミヤを通して語られたしたとおりに成されたのを見て驚き、それが神の御業であると認めたのです。あなたも神のみことばに信頼し、神のみこころに従うなら、必ず神の御業を見るようになるのです。
私たちは、1983年に福島で開拓伝道をスタートしましたが、翌年から仕事を辞め仙台の神学校で学ぶことになったので、生活のために家で英会話クラスを始めるにしました。とはいっても、実質的にはやったのは私ではなく家内でしたが・・。そこに1人の年輩の男性の方で石川さんという方が来られました。この方は衣料品の卸業を営んでおられる方でしたが、以後、私たちが大田原に来るまでの20年間、ずっと学び続けてくれました。最初に来られた時はもう60を過ぎていましたから、その後20年というと、とうに80を超えていたかと思います。私たちは今でもこの方の話をすることがあります。どうして石川さんは私たちのところに来られたのかねと。
実はこの方の亡くなられた奥様がクリスチャンでした。そして奥様が通っておられた教会の牧師が、奥様の命日に毎年この方のお宅を訪れて祈ってくれていたんですね。そのことをよく私たちに話しておられました。だから私たちの家がボロボロの借家でも、看板に十字架があるということで信頼して来てくれたのだと思っていました。しかしある時、それもあったかと思いますが、それは神様が送ってくださったんだと確信するようになりました。
というのは、その後教会で会堂建設に取り組むことになりますが、私たちが建てようとしていた土地が調整区域といって建物を建てることができない土地だったのですが、この方の一言で大きく前進することになったからです。県から開発許可を受けることが難しく、もう止めようと諦めかけていたとき、英語のクラスの後でこの方が「だったらあの方にお話してみたら」と言われたのです。その方は県会議員をしている方でしたが宅建の資格を持っていて、その免許の更新の時によくお話する間柄だということでした。私も全然知らない方ではなかったので早速電話をしてみると、「一応、話だけはしてみます」ということでした。するとしばらくして県の担当者から連絡があり、申請に必要な書類を持って来てほしいと言われました。そして、ついに1997年11月に開発許可が下りたのです。それは祈り始めてから4~5年後のことでした。
私はその時、神様から与えられていたみことばを思い出しました。それは創世記26章22節のみことばです。
「イサクはそこから移って、もう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。「今や、主は私たちに広い所を与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。」
これはイサクがペリシテの地に井戸を掘ったとき彼らから出て行ってほしいと言われ、仕方なく今度はゲラルの谷間に井戸を掘ると、ゲラルの羊飼いたちから「この水はわれわれのものだ」と言われて争いとなったため、仕方なくもう一つの井戸を掘らなければなりませんでした。それがこのレホボテです。意味は「広々とした地」です。イサクにとってそれは三度目の正直でしたが、私たちも開拓してから三度目の場所でした。しかもそこは600坪もある広々とした土地でした。ですからそれは私たちに対する神様からの約束だと受け止めましたが、すっかり忘れていたのです。しかし、こういう形で与えられたとき、そのみことばを思い出しました。あり得ないことです。でも神様はこのみことばの約束のとおりにしてくださいました。そのために神様は彼を送ってくださったのです。
20年ですよ。どうして神様は彼を送ってくださったのかわかりませんでしたが、後でわかりました。このためだったんだと。もちろん、伝道しましたよ。毎週英語のクラスの後で自然な会話をしながら、その中でイエス様を信じてくださいと勧めました。でも最後まで信じませんでした。決して受け入れたくないというわけではありませんでした。信じるならキリスト教だと思っていましたから。でもそのように勧める度にいつも笑ってこう言うのでした。「はい、自分が死ぬちょっと前に信じますから。」と。そんなのいつかわからないじゃないですか。今が恵みの時、今が救いの日です、と勧めましたが、結局私たちが大田原に来るまで信じることはありませんでした。そして、こっちに来てからその方が召されたことを知りました。本当に残念です。あんなにいい方で、あんなに神様に心を開き、あんなに教会のためによくしてくださった方なのに、イエス様を信じなかったのは本当に残念だと思いました。でも、その中でも神様は働いておられ、ご自身の御業を進めてくださったのです。神にはどんなことでもできること、どのような計画も不可能ではないことを、私は知りました。
あなたにとって難しい、できないと思っていることは何ですか。でも神様にはどんなことでもおできになられます。ですから私たちは神を信じて、神のことばに信頼しなければなりません。そうすれば、あなたも神の御業を見るようになるのです。
Ⅲ.クシュ人エベデ・メレクの救い(15-18)
最後に、15~18節をご覧ください。
「15 エレミヤが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミヤに次のような【主】のことばがあった。16 「行って、クシュ人エベデ・メレクに言え。『イスラエルの神、万軍の【主】はこう言われる。見よ、わたしはこの都にわたしのことばを実現させる。幸いのためではなく、わざわいのためだ。それらはその日、あなたの前で起こる。17 しかしその日、わたしはあなたを救い出す──【主】のことば──。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。18 わたしは必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたのいのちは戦勝品としてあなたのものになる。あなたがわたしに信頼したからだ──【主】のことば。』」」
クシュ人エベデ・メレクについては、前の章の38章7~13節で学びました。エレミヤが泥の中に沈みかけていた時、彼がエレミヤをその泥の中から救い出したという話です。ですから時間的な順序で言うなら、この箇所はその直後に記されるべき内容です。それがここに記されてあるのは、おそらくこのエルサレムの崩壊に際して、エベデ・メレクが行ったことに対する神の報い、神の約束が成就したことを記すためだったのではないかと思います。エレミヤが泥の中から救い出された時、彼は監視の庭に閉じ込められていましたが、その時このクシュ人エベデ・メレクに対して、16~18にある預言がエレミヤを通して語られたのです。それは17節にあるように、主は必ず彼を救い出す、助け出すということです。「あなたのいのちは戦勝としてあなたのものになる」というのは、「いのちだけは助かって生き残る」という意味です。新共同訳ではそのように訳されています。彼はその危機を生き延びて、その生涯を平安のうちに終えたと理解することができます。いったいなぜ彼はその危機から救い出されたのでしょうか。
18節にその理由が次のように記されてあります。「あなたがわたしに信頼したからだ。」
それは、彼が主に信頼したからです。彼は異邦人でありながら、イスラエルの神、主に信頼しました。だから、彼は助け出されたのです。彼がエレミヤを泥の中から助け出したのも、それは彼が主に信頼していたからだったのです。それで彼は神からの祝福を受けたのです。
それは私たちも同じです。実はこの異邦人エベデ・メレクは私たちの型というか、私たちのモデルなのです。というのは、私たちもイスラエルの民からすれば異邦人であり、神から遠く離れていた者であったにも関わらずイエス・キリストを信じたことによって神の民とされ、神の祝福を受け継ぐ者とされたからです。主イエスを信じる者は救われます。彼に信頼する者は失望させられることはありません。エペソ人への手紙2章11~13節にはこうあります。
「ですから、思い出してください。あなたがたはかつて、肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる「割礼」を持つ人々からは、無割礼の者と呼ばれ、そのころは、キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく、神もない者たちでした。しかし、かつては遠く離れていたあなたがたも、今ではキリスト・イエスにあって、キリストの血によって近い者となりました。」
私たちもかつてはキリストから遠く離れ、イスラエルの民からは除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって何の望もなく、神もない者でした。しかし、そのような私たちもキリストの血によって神に近い者、いや、神の民とされたのです。それは一方的な神の恵みによるのです。その神の恵みを受けてエベデ・メレクが神に信頼し、エレミヤを助けたように、私たちもキリストの血によって神の民の一員として加えられ、神に信頼する者とされました。それゆえ、神の祝福を受ける者とされたのです。
であるなら、私たちの人生において最も重要なことは何でしょうか。それは私たちがどういう者であるかとか、どれだけ力があるかということではなく、誰と共に歩むのかということです。何に信頼して歩むのかです。
あなたは何に信頼していますか。誰と共に歩んでおられるでしょうか。主に信頼する者は守られます。「しかしその日、わたしはあなたを救い出す─主のことば─。あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。わたしは必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたのいのちは戦勝品としてあなたのものになる。あなたがわたしに信頼したからだ─主のことば。」
もしかすると、あなたはエレミヤのように泥の中に沈みかけているかもしれません。お先真っ暗ですと。でも主に信頼するなら者は守られます。決して失望することはありません。それが神のことば、聖書があなたに約束していることです。神様は異邦人エベデ・メレクを救い出したように、またエレミヤを助けてくれたように、必ずあなたを救い出し、助け出してくださいます。私たちも主に信頼しましょう。それはあなたがだれに信頼したかによって決まるのです。
カテゴリー: Uncategorized
一つになってともに生きる幸い 詩篇133:1~3節
聖書箇所:詩篇133:1~3節
タイトル:「一つになってともに生きる幸い」
主の2025年、明けましておめでとうございます。この新しい年も皆さんとご一緒に礼拝することを感謝します。皆さんはどのような思いで新年を迎えられたでしょうか。今年も主の栄光が現わされるように、主のみことばに聞き従い、みことばに歩んでまいりましょう。
この新年礼拝で私たちに与えられているみことばは、詩篇133篇のみことばです。1節には、「見よ。なんという幸せ なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって、ともに生きることは。」とあります。
皆さん、何が幸せなんでしょうか。何が楽しみなのでしょうか。それは、兄弟たちが一つになって、ともに生きることです。これが主のみこころです。これが今年私たちに求められていることです。私たちは今年、一つとなってともに生きることを求めていきたいと思います。そして、それによってもたらされる主の祝福がどれほど大きいかを味わいたと思うのです。
きょうは、この「一つとなってともに生きる幸い」について、三つのことをお話したいと思います。第一に、兄弟たちが一つとなってともに生きることは実に幸いなことであり、実に楽しいことであるということです。第二に、それはどれほどの幸いなのでしょうか。それは、頭に注がれた貴い油がアロンのひげに、いやその衣の端にまで流れ滴るほどです。また、ヘルモンからシオンの山々に降りる露のようです。どうしてそれほどの祝福が注がれるのでしょうか。それは、主がそこに、とこしえのいのちの祝福を命じられたからです。ですから第三のことは、私たちも一つになって、ともに生きること求めましょう、ということです。
Ⅰ.一つになってともに生きる幸い(1)
まず、兄弟たちが一つとなってともに生きる幸いから見ていきましょう。1節をご覧ください。ご一緒にお読みしたいと思います。
「133:1見よ。なんという幸せ なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになってともに生きることは。」
この詩篇の表題には、都上りの歌。ダビデによる、とあります。この詩篇の作者であるダビデは、「見よ」という呼びかけでこの詩を始めています。とても印象的な表現ではないでしょうか。「見よ。なんという幸せ、何という楽しさであろう。」それはこれを読む人たちに、このことを何としても伝えたい、何としても知ってほしい、という思いが込められているからです。
その思いとは何でしょうか。それは、兄弟たちが一つになって、ともに生きることの幸いです。それはなんという幸せ、何という楽しさであろうか、というのです。ここでダビデは、「なんという」ということばを繰り返すことによって、兄弟たちが一つになってともに生きることの幸いを強調したかったのです。
皆さん、どうでしょうか。兄弟たちが一つになって、ともに生きること、ともに礼拝することは、それほど幸いなこと、それほど楽しいことだと考えたことがあるでしょうか。いや、私はいいです。私はひとりで聖書を読んでいた方が幸せなんです。第一面倒くさいです。他の人に気を使わなければならないし。だったらひとりでいた方がどれほど楽なことか・・・。そういう思いはありませんか。でもここにはそのようには言われていません。兄弟たちが一つになって、ともに生きることは、なんという幸せ、何という楽しさであろうか、と言われているのです。これは、「都上りの歌」です。都上りの歌とは「巡礼の歌」のことです。主の宮に集まって、主を礼拝すること。それはなんという幸せ、なんという楽しさであろうかというのです。
皆さん、兄弟姉妹が一つとなって主の宮に集まり、ともに主を礼拝することはそれほど楽しいこと、それほど幸せなことなのです。先々週のクリスマス礼拝では、私たちの主イエスは「インマヌエルの主」として生まれてくださったということをお話しました。意味は何でしたか。意味は、「神は私たちとともにおられる」です。私たちはひとりぼっちではありません。イエス様が私たちとともにいてくださいます。嵐の時も、穏やかな時も、いつもイエス様がともにいてくださるのです。それは本当に幸いなことではないでしょうか。けれども、私たちにはそれだけではないのです。それとともにすばらしい祝福が与えられているんです。それは同じ神を信じる兄弟姉妹たちがともにいるということです。
私たちには、ともに生きる神の家族が与えられているのです。不思議ですね、教会って。年齢も、性別も、出身地も、国籍も、みんな違いますが、イエス様を信じたことによって天の神を「アバ」、「お父ちゃん」と呼ぶことができるようになったことによって、お互いが兄弟姉妹とされたのです。どっちが兄で、どっちが弟なのかわからない時もありますが、みんな兄弟姉妹です。相手の名前がわからない時はいいですよ。「兄弟」とか「姉妹」と呼べばいいんですから。最近はなかなか名前が思い出せなくて・・という方は、ただ「兄弟」と呼べばいいので簡単です。特に私たちの教会には世界中からいろいろな人たちが集まっているので、名前を覚えるのは大変です。でも「Brother」とか「Sister」と呼べば失礼にならないので助かります。こうして主イエスを信じる世界中のすべての人と兄弟姉妹であるというのはほんとうに不思議なことです。英語礼拝を担当しているテモシー先生はガーナの出身ですよ。肌の色も違う。何歳かもわかりません。でも兄弟と呼べるというのはすごいことだと思うんです。このように自分と全く違う人たちがイエス・キリストによって一つとされ、ともに生きることは、ほんとうに幸せなこと、ほんとうに楽しいこと、これ以上の幸いは他にはないというのです。
この詩篇は歴史を通してユダヤ人たちにとても愛されてきた、大切にされてきた詩篇なんです。どうしてかというと、ユダヤ人たちは離散の民だったからです。かつてユダヤ人たちは神殿、神の宮ですね、神の宮に集まって主を礼拝していましたが、それが彼らにとって何よりも喜びだった。何よりも幸せだったのです。
ところが、その後ユダヤ人たちは国を失ってしまいました。みんなバラバラになってしまった。多くの人たちが捕囚の民として、外国に連れて行かれました。バビロン捕囚です。他の国に散らされて行った人たちもいます。その置かれた場所で咲きましょう、ではありませんが、彼らは旧約聖書の律法を大切なしながら、そこで信仰を育んでいったのです。
けれども彼らは、かつてのようにみんなで集まって礼拝することができなくなってしまいました。そんなユダヤの民にとってこの詩篇133篇は、かつて彼らが味わった幸せを懐かしく思い出す歌となったのです。そしていつの日か、今はまだその時ではないけれども、もう一度この幸せを味わうことができる日がくる、そんな希望を覚える歌として、大切にされてきたのです。
そのようにしてユダヤ人たちは、自らの過去と未来の両方を思いながらこの歌を味わい、この歌を歌いながら、また希望に思いを馳せながら、共に集まることの幸いを味わっていたのです。
ドイツの牧師で神学者のボンヘッファーは、この詩篇133篇から「ともに生きる生活」という本を書いていますが、その本の中で彼は兄弟姉妹が共に集まって生きることの幸い、そして教会の祝福についてこのように言っています。
「キリスト者の兄弟姉妹の交わりは、日ごとに奪い去られるかもしれない神の恵みの賜物であり、ほんのしばらくの間与えられて、やがて深い孤独によって引き裂かれてしまうかもしれないものであるということが、とかく忘れがちである。だからその時まで他のキリスト者とキリスト者としての交わりの生活を送ることを許された者は心の底から神の恵みをほめたたえ、跪いて神に感謝し、我々が今日なおキリスト者の兄弟との交わりの中で生きることが許されているのは恵みであり、恵み以外の何ものでもないことを知りなさい。」
皆さん、これは当たり前のことじゃないのです。兄弟姉妹が一つになってともに生きること、ともに主を礼拝できるというのは神の恵みなんです。恵みの賜物以外の何ものでもない。私たちはこうして毎週集まって礼拝をささげていますが、これはいつ奪い取られるかわからないことなのです。たとえば、新型コロナウイルスが発生した時、多くの教会では集まることができませんでした。そうした教会の中には、それ以降集まることが困難になって閉鎖した教会も少なくありません。当たり前じゃないのです。それは本当にかけがえない恵みであり、本当に幸いなことなんだと、ボンヘッファーは言ったのです。
皆さん、兄弟たちが一つになってともに生きることは、なんという幸せ、何という楽しさでしょうか。そうなんです。兄弟たちがバラバラに歩むのではなく一つになってともに生きることは、本当に幸いなことなのです。文化や習慣、考え方、性格など、それぞれの違いがありながら互いに調和を保っていくことは簡単なことではありませんが、しかしそうした違いを乗り越えて一つなってともに生きることは、本当に幸いなことであり、これ以上の祝福はありません。
Ⅱ.主が注がれるとこしえのいのちの祝福(2-3)
では次に、その祝福がどれほどのものなのかを見ていきましょう。この詩篇の著者はその祝福のすばらしさを、次のように語っています。2節と3節をご覧ください。ご一緒にお読みしましょう。
「133:2 それは頭に注がれた貴い油のようだ。それはひげにアロンのひげに流れて衣の端にまで流れ滴る。
133:3 それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。【主】がそこにとこしえのいのちの祝福を命じられたからである。」
ここには、それは頭に注がれた貴い油のようだとあります。また、それはヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ、とあります。どういうことでしょうか。それほど麗しい豊かな祝福だという意味です。なぜなら、それはただの人間的な楽しさとは違うからです。そこには主のとこしえのいのちの祝福が流れているからです。
まずそれは、頭に注がれた貴い油のようだと言われています。それはひげに、アロンのひげに流れて、衣の端にまで流れ滴ると。どういうことでしょうか。それほど神様の祝福に潤される、満たされるということです。
頭に油を注ぐというのは、整髪料じゃあるまいし、私たち日本人にはあまりピンとこないかもしれませんが、ユダヤの地方には、そういう習慣がありました。福音書の中にも、イエス様の頭に油を注いだ人がいますね。誰ですか? そう、ベタニアのマリアです。彼女はイエス様にいたずらをしようと思ってやったわけではありません。イエス様を驚かせようとしたわけでもないのです。イエス様に対する愛と感謝を表すためにしたのです。その香油はあまりにも高価なものだったので、それを見ていた弟子の一人のイスカリオテのユダは、「どうして、そんな無駄なことをするのか。この香油なら300デナリ(300日相当の労働の対価)で売れるのだから、それを貧しい人に施せばいいじゃないか」、と言って憤慨したほどです(ヨハネ12:5)。香油というのはそれほど高価のものでした。それほど高価な香油を、彼女はイエス様の頭にガバッーと注いだのです。ですからイエス様はそのことをとても喜ばれ、彼女の行為を高く評価されたのです。
しかしここでは、それはただの香油ではないことがわかります。ここには「アロンのひげに流れて」とあります。アロンとはモーセのお兄さんのことですが、彼は大祭司として任職されました。その任職式の時に油が注がれたのです。それがこの貴い油です。その時の様子がレビ記8章12節にありますが、その量は中途半端なものではありませんでした。大量の油が注がれたのです。それがどれほどのものであったかを、ここでは何と表現されていますか。それはアロンのひげに流れて、とあります。さらにはアロンの着ていた衣の端にまで流れ滴る、とあります。アロンの胸には大祭司が身に着けるエポデという胸当てがありましたが、そこにはイスラエル12部族を表わしている12の宝石が埋め込まれてありました。アロンの頭に注がれたその貴い油はアロンのひげに流れると、そのエポデも全部覆って、やがてアロンが着ていた衣の端にまで流れ滴ったのです。それほど豊かな油であったというのです。ここでは「流れて」とか「流れ滴って」とことばが繰り返されてありますが、それは、上から下へと流れる、天の神様の祝福の豊かさを強調されているのです。そしてその祝福こそが教会に流れている幸せと祝福の源なのです。
さらにその祝福は、もう一つのたとえによっても描かれています。それはヘルモン山から下りる露です。3節をご覧ください。ご一緒に読んでみましょう。
「133:3 それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。」
ヘルモン山というのは、ガリラヤ湖の北東約50キロにある山です。標高は海抜2,814メートルと言われていますから、相当高い山です。ですから、その山頂は万年雪となっていて夏でもスキーができるほどなんです。一方、シオンの山々とはというと、イスラエルの南、死海近辺にあるエルサレムの山々のことです。そこは草も生えないような乾燥地帯、山岳地帯となっています。そこがヘルモンの山頂にある雪解けの水が露となって滴り落ち、潤されるようだというのです。どういうことでしょうか。
実際にはヘルモン山から南のシオンの山々までは約200キロメートルも離れていますから、その山の露がシオンの山々にまで降りるということは考えられません。でも神様の祝福というのはそんな人間の理解とか想像も及ばないほど豊かで、まるでヘルモンの山からシオンの山々にまで降り注ぐ大量の露のようだというのです。兄弟たちが一つとなってともに生きることは、それほど私たちを豊かに潤してくださるということです。どんなにカラカラに乾いていても、神様の祝福というのは、そんな乾いた全地を潤すほどの祝福なのです。
ところで、この3節にある「降りる」という言葉ですが、これは2節に出て来た「流れる」という言葉と同じ言葉です。ですから、この詩篇の作者はこのことばを3回も繰り返すことによって、上から下へと注がれる神様の祝福がどれほど豊かであるかを表したかったのです。どうしてそんなに豊かなのか。それは、主がそこにとこしえのいのちの祝福を命じられたからです。その恵みの大きさを覚えて主に心から賛美を捧げようではありませんか。
兄弟たちが一つになって、ともに生きることは、それほどの幸せ、それほどの楽しさなのです。カラカラに渇いているあなたのたましいまでも満たしてくれる。そういうまさに天来の祝福、天来の幸せ、天来の喜びで溢れるのです。
Ⅲ.一つになってともに生きる(3)
であれば第三のことは、私たちも一つになって、ともに生きることを求めましょう、ということです。もう一度3節の最後のことばに注目してください。ここには、「主がそこに、とこしえのいのちの祝福を命じられたからである。」とあります。
私たちが互いに愛し合う、その交わりの中に、主がとこしえのいのち、永遠のいのちの祝福を注いでくださいます。なぜなら、それは何よりも神様のみこころであり、そのために私たちは召されているからです。それなのに、私たちの側で心の眼が曇らされてしまって、互いにさばき合ったり、ねたみ合ったりして、こんなにも豊かな神様の祝福を閉ざしてしまうことがあるとしたら、何ともったいないことでしょう。ですから私たちはこの詩篇の作者が「見よ」と呼び掛けて、「なんという幸せ、なんという楽しさだろう」と、声を大にして伝えているこのこと、すなわち兄弟たちが一つになって、ともに生きるというこの歩みを、大切にしていきたいと思うのです。いつでもこの教会を、神様のとこしえのいのちの祝福が覆ってくださるように、そしてそれを私たちが豊かに感じながら、ただ神様に感謝と礼拝をささげていくことができるように、私たちは一つになってともに生き、その祝福の流れに乗り続けていきたいと思うのです。
いったいどうしたらそんな歩みができるのでしょうか。その鍵は「御霊によって一致」することです。パウロはエペソ4章1~3節の中でこのように勧めています。
「4:1 さて、主にある囚人の私はあなたがたに勧めます。あなたがたは、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。
4:2 謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び
4:3 平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。」
ここでパウロは、エペソの兄弟たちに対して、召された者はその召しにふさわしく歩むようにと勧めています。召しとは救いへの召しのことです。かつては罪の奴隷であった者が、そこから解放されてキリストのしもべとして召されました。それがクリスチャンです。クリスチャンとは「キリストのしもべ」という意味です。私たちはイエス様を信じたことでクリスチャンとして召されたのです。ですから、その召しにふさわしく歩まなければならないのです。それはどのような歩みでしょうか。ここには、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、同じ神の霊、聖霊を受けている者として、御霊による一致を熱心に保ちなさい、とあります。私たちが頑張って一致するというのではありません。私たちはそのように召された者なのだから、キリストにある者とされたのだから、そり召しにふさわしくキリストにあって歩むのです。それが召しにふさわしい歩みです。それが、御霊による一致を保つということなのです。
それは、言い換えると「互いに愛し合う」ということです。主イエスはこう言われました。
「13:34 わたしはあなたがたに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。
13:35 互いの間に愛があるなら、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての人が認めるようになります。」(ヨハネ13:34~35)。
イエスが愛したように、私たちも互いに愛し合うこと、それが、主イエスが命じておられることです。ここには「新しい戒め」とありますね。これは新しい戒めなんです。古い戒め、すなわち旧約聖書の中にも隣人を愛さなければならない、という戒めがありました。たとえば、レビ記19章18節には、「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。」とあります。ですから、互いに愛し合うとか、隣人を愛するというのは別に新しい戒めではないはずなのです。それなのにどうしてイエスはこれを新しい戒めと言われたのでしょうか。それはどのように愛するのかという点においてです。確かに旧約聖書にも「あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい」とありますが、イエス様が言われたのは、あなたの隣人を、あなた自身のように愛しなさいというのではなく、「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛しなさい」ということでした。あなたの隣人をあなた自身のように愛するというのは、あなたが自分を愛するのと同程度に愛するということですが、イエスが愛したように愛するというのは、それを越えているのです。そのように愛しなさいというのです。
ではイエス様はどのようにあなたを愛してくださったのでしょうか。イエス様は弟子たちにその模範を示されました。それが弟子たちの足を洗うという行為でした。それはただ兄弟姉妹の足を洗い合えばいいのかというとそういうことではなく、そこに込められている意味を実践しなさいということです。それは何でしょうか。それはしもべとして生きるということです。イエス様はしもべとして死に至るまで相手に仕えられました。その究極が十字架だったのです。聖書は十字架を指してこう言っています。
「私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。」(Ⅰヨハネ4:10)
皆さん、どこに愛があるのでしょうか。聖書は「ここに愛がある」と言っています。それは、私たちの罪のために、宥めのささげ物として御子を遣わされたことの中にあると。神の愛はイエスの十字架によって完全に表されました。多くの人は、「愛」を表すのに、「ハート」の形を使いますが、聖書的にいうなら、愛の「形」は、「ハート」ではなく、「十字架」です。イエス様は、この十字架の愛に基いてこう言われたのです。「互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。」と。これは言い換えると、一つになって共に生きるということです。私たちが一つになってともに生きるなら、それによって私たちがキリストの弟子であることを、すべての人が認めるようになるのです。
元旦の朝、私たち夫婦はいつものように二人で一緒に聖書を読んで祈りました。新年の最初の日ですから、神様はどんなみことばを与えてくださるかと期待して開いた聖書箇所は、エゼキエル書5章でした。そこにはバビロンに連れて行かれた預言者エゼキエルが、エルサレムに向かって神のさばきを語るという内容でした。新年から神のさばきかとちょっとがっかりしましたが、そこに神のみこころが記されてありました。それは、イスラエルの民が置かれている所はどこか、ということです。5章5節にこうありました。
「神である主はこう言われる。「これがエルサレムだ。わたしはこれを諸国の民のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした。」」
彼らが置かれていたところはどこですか。これがエルサレムです。主は彼らを諸国のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした、とあります。何のためでしょうか。それは彼らが主のみこころに歩むことによって、そうした周りの国々も主を知り、主に立ち返るようになるためです。それなのに、自分たちが選ばれたことに優越感を持ちその使命を果たすことをしなかったら、主はどれほど悲しまれることでしょうか。事実、エルサレムは神の定めを行いませんでした。それどころか、彼らの周りの国々の定めさえも行わなかったのです。それゆえ、主は彼らをさばかれたのです。
これを読んだ時、それは私たちにも言えることではないかと思わされました。私たちがここに置かれているのは何のためでしょうか。それは、私たちを闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方のすばらしい栄誉を告げ知らせるためです。それなのに、その使命を忘れ、自分が好きなように、自分がしたいように生きるとしたら、それこそイスラエルと同じではないかと思ったのです。神によって救いに召された私たちに求められていることは、このすばらしい神の栄誉を告げ知らせることです。どうやって?互いに愛し合うことによってです。互いの間に愛があるなら、それによって私たちがキリストの弟子であることを、すべての人が認めるようになります。私たちは今年、そのような年になることを求めていきたいと思います。
昨年のクリスイヴのことですが、と言ってもつい2週間ほど前ですが、その日に2人の方からお電話をいただきました。「今晩は、クリスマス礼拝がありますか」と。一人は日本人の女性の方で、これまで一度も教会に行ったことがないという方でした。もう一人はインドの方で、クリスチャンの方でした。仕事で東京から来ているがクリスマス礼拝があれば行きたかったということでした。やはりクリスマスは人々の心が開かれる時なんだなぁと思いましたが、ふと、今年のクリスマスを私はどのように過ごしたらよいか、どのように過ごすことを神は願っておられるかという思いが与えられました。勿論、家族で過ごすのもすばらしいことです。でもそれだけでよいのか、教会に来たくても来れない方がいるならその方を訪問して一緒に礼拝することを、神は喜ばれるのではないかと示され、施設に入所している方々を訪問することにしたのです。それは私が目の手術で入院していた時、誰にも会うことができないという状況の中で、深い孤独と寂しさを経験したからです。
最初に下野姉が入所している施設を訪問しました。下野姉を訪問したのは2回目でしたが、本当に喜んでくれました。マタイの福音書から私たちの主はインマヌエルとして来てくださり、いつも下野さんとともにおられますから安心してくださいとお祈りすると、帰りに「先生、握手」と握手まで求められ、掴んだ手をずっと握り締めて離しませんでした。それほど不安だったんでしょう。それほど寂しかったんでしょう。最後に「先生、その時にはよろしくお願いします」と言われました。それはご自分が主のもとに行かれる時のことを言っておられるんだなぁと思い、「わかりました。大丈夫です。安心してください」と言ってお別れしました。
その足で和気姉が入所している施設に向かいました。和気姉もだいぶお身体が弱くなり、こちらから話しかけてもあまり応答できなくなりましたが、クリスマスなので一緒に賛美しましょうと「きよしこの夜」を歌うと、「きよし、このよる」と、自分のすべての力をふり絞るかのように大きな声で賛美されました。驚きました。じゃ、もう一曲賛美しましょうと、次に「雨には栄え」と賛美すると、これも大きな声で歌われたのです。何も覚えていないようでも賛美歌は覚えておられるんだ、と感動しました。私は時間のことを心配していましたが、もう時間のことも忘れてしまうくらいそこには神の臨在と祝福が満ち溢れ、さながら天国にいるかのような心地でした。まさに兄弟が一つとなってともに生きることは、なんという幸い、なんという楽しさでしょう。これ以上のない喜び、楽しさ、幸せはありません。
皆さん、私たちはこれまでもそうであったように、これからも互いに愛し合い、一致し、ともに生きる、ともに歩んで行く、そんな教会でありたいと思います。あり続けたいと思います。それはなんという幸せでしょうか。なんという楽しさでしょうか。それほど幸せなことはありません。それほど楽しいことはない。それほど麗しい交わりはありません。ともにそのような教会を目指してまいりましょう。それが今年私たちに求められていることなのです。
その名はインマヌエル マタイ1章18~25節、イザヤ7章10~17節
クリスマス礼拝メッセージ
聖書箇所:マタイ1章18~25節、イザヤ7章10~17節
タイトル:「その名はインマヌエル」
クリスマスおめでとうございます。私たちのために御子イエスをこの世に送ってくださった主なる神に感謝し、心から御名をほめたたえます。今日はクリスマス礼拝ですが、こうして愛する皆さんとともに主を礼拝できることを感謝します。
今日はマタイの福音書1章とイザヤ書7章から、「その名はインマヌエル」というタイトルでお話したいと思います。これは非常に重要なテーマです。というのは、聖書全体を貫いている中心的なメッセージだからです。
皆さん、キリスト教の中心は何か、聖書全体のメッセージを一言で言うとしたら何かと尋ねられたら、何と答えるでしょうか。私なら、こう答えます。それは「インマヌエル」である、と。すなわち、「神が私たちとともにおられる」という約束です、と。これが聖書全体の中心的なテーマです。これがイエス・キリストの誕生によって実現しました。だからクリスマスは意味があるのです。
きょうは、この「インマヌエル」について三つのことをお話したいと思います。第一に、私たちのためにお生まれになられた主イエスはインマヌエルの預言を成就するために来られたということ。
第二に、私たちの人生における真の解決は、このインマヌエルとして来られた主イエスにあるということ。
ですから第三のことは、主イエスをあなたの罪からの救い主として受け入れてください、ということです。
Ⅰ.その名はインマヌエル(マタイ1:18-23)
まず、マタイの福音書1章18~23節を見ていきましょう。18節をご覧ください。
「イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった。」
マタイの福音書はイエス・キリストの系図を記した後、「イエス・キリストの誕生は次のようであった」という文で始まっています。イエス・キリストはどのように誕生したのでしょうか。ここには、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分かった、とあります。それがどのようにして明らかになったのかはわかりません。そのことについて聖書は何も語っていないからです。でも、おそらくマリア自身がヨセフに伝えたのでしょう。
当時、ユダヤにおいては、婚約は結婚とほとんど同一視されていました。婚約していれば一緒に住んでいなくとも、二人は法的に夫婦とみされていたのです。一緒に暮らしてもいない妻マリアが身ごもったと聞いたとき、ヨセフはどんな気持ちだったでしょうか。それは私たちには想像できないほど苦しかったに違いありません。
結婚していないマリアが身ごもった、しかも聖霊によって身ごもったというではありませんか。それを聞いたヨセフは、ただ自分は裏切られ、マリアが姦淫の罪を犯したとしか考えられなかったでしょう。聖霊によって身ごもったというマリアの言葉を受け入れることなど到底できなかったはずです。このマリアに対して、いったい自分はどうすれば良いのか、悩みに悩みました。そして行き着いた結論は、ひそかに離縁する、ということでした。それが19節にあることです。19節をご覧ください。
「夫のヨセフは正しい人で、マリアをさらし者にしたくなかったので、ひそかに離縁しようと思った。」
ヨセフはマリアを本当に愛していたのでしょう。ですからそれを表ざたにしてマリアがさらし者となり、辱められて、石打ちの刑で処刑されることなど、耐えがたいことだったのです。しかし、ここに「夫のヨセフは正しい人で」とあります。この「正しい人」というは、律法に忠実に従うという意味での正しさのことです。ですから彼は、律法を破り、姦淫の罪を犯したとしか思えないマリアを受け入れることもできませんでした。それでどうしたでしょうか。それでヨセフは悩みに悩んで、ひそかに離縁しようと決めたのです。
しかし、彼がそのように決断した時、神がご介入されました。20節をご覧ください。
「彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。」
彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言いました。「ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。」と。
ルカの福音書においてマリアに対して語られたように、ここでも主の使いはヨセフに「恐れるな」と語られました。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいと。なぜなら、その胎に宿っている子は聖霊によるからです。どういうことですか?
ヨセフの苦しみは、マリアの胎の子はいったいだれの子なのか、どうして身ごもってしまったのかということでした。それに対して神が言われたことは、それは聖霊によるのだ、ということでした。聖霊によって宿ったのだ、と。つまり、神がそれをなさったのだということです。だからそれ以上思い悩む必要はない、というのです。主の使いはさらに続けてこう言いました。21節です。
「マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。」
聖霊によって身ごもったというマリアの言葉を信じられず、また、愛しているのにも関わらず、身重であるマリアを見捨てるというヨセフの「正しさ」は、ここで神によって完全に打ち砕かれることになります。律法に従うだけの「正しい人」であったヨセフは、この驚くべき出来事をご自分の民をその罪から救うために実現された神の御業である信じ、この主に従って生きるようにと求められたのです。聖霊によって身ごもったマリアを迎え入れ、生まれた男の子に「主は救いである」という意味を持つ「イエス」という名前を付けなさいという命令が与えられたのです。
このようにクリスマスの出来事においては、マリアだけではなく、ヨセフにも神から大きな役目なり、使命が与えられていたことがわかります。それは聖霊によって身重になったマリアを受け入れ、支え、守り、そして、生まれてくる男の子には「イエス」と名付けるという役目です。そして、ヨセフは自分には理解できなくとも、この主の命令に従います。24~25節にあるように、眠りから覚めたヨセフは、主の使いが命じたとおりに、自分の妻マリアを受け入れ、生まれた男の子に「主は救いである」意味持つ「イエス」という名前を付けたのです。
重要なのは、この一連の出来事は何ために起こったのかということです。これを書いたマタイは、この一連の出来事はただ偶然に起こったことではなく、旧約聖書に預言されていたみことばが成就するためであったと告げるのです。それが22~23節にある内容です。ご一緒に読みましょう。
「22 このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。23 「見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」それは、訳すと「神が私たちとともにおられる」という意味である。」
このすべての出来事、つまり、まだ一緒に住んでいないマリアが身ごもったという出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった、ということです。その預言とは、皆さんもよくご存知のように、旧約聖書イザヤ書7章14節の御言葉です。そして重要なのは、その名は「インマヌエル」と呼ばれるということです。意味は、「神は私たちとともにおられる」という意味です。つまり、ご自身の民をその罪から救うためにお生まれになられたイエスは、イザヤ書で約束されていた「インマヌエル」、「神は私たちとともにおられる」という約束を実現してくださる方であるということです。
このことは、とても重要です。というのは、聖書で言うところの「救い」とは何かを明確に表しているからです。つまり、聖書で言う「救い」とは、罪が赦されて永遠のいのちが与えられることですが、それは、言い換えると「神がともにおられる」ということなんです。これが聖書で言う「救い」です。私たちが「救われる」という言葉を用いるとき、それはたとえば病気が癒されることとか、貧乏から解放されること、あるいは、何らかの問題が解決することを言いますが、聖書で言うところの救いとはそうした問題の解決ばかりでなく、そうした問題の根本的な原因である罪からの救いを意味しているのです。つまり、これが本当の解決であるということです。
確かに病気が癒されることも素晴らしいことです。私も眼の病気で苦しみかなり落ち込みましたが、一昨日抜糸のため病院へ行ったら眼圧が下がっていて、正常の数値になっていました。本当にうれしかったですね。
貧乏から解放されることもそうです。借金地獄という言葉もありますが、抱えている借金を完済してゼロになったらどんなに解放されることでしょう。あるいは、家庭の問題や職場の問題、人間関係の問題が解決したらホッとするでしょう。しかし、本当の解決はそうした問題の根本にある罪から救われることなのです。
そして、ヨセフが聖霊によって身重になったマリアを妻として迎え入れたことによって、そのことが実現しました。この男の子は人間的にはあり得ないことですが、人間的な方法によってではなく聖霊によってマリアの胎に宿りました。それはこの方がご自分の民をその罪から救ってくださるためです。神は聖なる、聖なる、聖なる方ですから、ちょっとでも罪や汚れがあるところには住まうことはできません。それで神は人間的な方法によってではなく、聖霊によって救い主イエスをマリアの胎に宿らせ、生まれさせることによって、その民を罪から救うという御業を開始されたのです。そしてこの方がその罪を負って十字架で死なれ、三日目によみがえることによってその救いの御業を完成してくださいました。それゆえ、この方を信じる人はだれでも罪から救われるのです。そうです、「インマヌエル」、「神は私たちとともにおられる」という約束を実現してくださったのです。ですから、この方を信じる者は罪から救われ、神がその人とともにいてくださいます。これが救いです。多くの人は「救われる」ということは、死んでから天国に行くことだと考えていますがそれだけではないんです。この世で生きていながらも、それを体験することができるのです。それはこの「神、共にいまし」です。あなたがこのイエスをあなたの罪からの救い主として信じるなら、その瞬間にあなたの罪は赦され、永遠のいのちが与えられます。「インマヌエル」、「神が私たちとともにおられる」が実現するのです。
「沈黙のレジスタンス」という映画をご覧になられた方はおられるでしょうか。これは実話を基にして作られた映画です。マルセル・マルソーという、パントマイムの巨匠の若き日々を描いたものです。実は彼は、フランスに生きるユダヤ人でした。第二次世界大戦中、ドイツではヒトラーが政権を握ると、国内のユダヤ人たちは次々と迫害の対象となりました。そして、ドイツの国内でたくさんのユダヤ人孤児が生まれるんです。
その孤児たちは、ユダヤ人組織によってフランスに送られて難を逃れるのですが、やがてフランスもナチスドイツに侵略され、併合され、占領されてしまいます。フランスに逃げてきたユダヤ人孤児たちの世話をしたのが、フランスユダヤ人のレジスタンス組織だったんですが、マルセル・マルソーはそのメンバーでした。
やがてナチスは、フランスに大きな力を振るうようになります。そして、フランス国内では、親ナチスの政権が誕生し、フランスのユダヤ人孤児たちも強制収容所に送られることになります。そこで、どこにも逃げ場がなくなったこのユダヤ人のみなしごたちを助けるためにある極秘プロジェクトが始まったんです。それは、フランスの隣にある、永世中立国のスイスに、この子どもたちを亡命させるというプロジェクトでした。しかし、通常の国境は、すでにナチスにコントロールされていました。そこで、マルセル・マルソーは、子どもたちにボーイスカウト、ガールスカウトの服を着させ、自分はそのリーダーになりすまし、ピクニックに行くように芝居を打って、フランス国外脱出をはかるのです。
ところが途中、ドイツ併合エリアを通らなければなりません。電車の中にナチスのゲシュタポ(秘密警察)が乗り込んで、身元調査を始めるんですが、ユダヤ人の孤児たちは、皆ゲシュタポに両親を殺されるのを見ていたので、その制服を見るだけで震え上がってしまうのです。しかし、すぐさま落ち着きを取り戻します。なぜなら、マルセル・マルソーがギューッと手を握ったり、ハグしたり、そして共にいて堂々とゲシュタポと渡り合うその対応を見たからです。そして、とうとうスイスに脱出することが出来たのです。
何を言いたいのかというと、共にいることは、勇気を与える最良の手段なであるということです。キリストは、死の世界から、永遠のいのちの天国にあなたを導くために来てくださいました。そしていつもあなたと共にいてあなたを助け、守り、励まして、あなたがこの地上での生涯を歩む上で必要な力を与えてくださいます。そしてあなたが死んでもあなたと共におられるインマヌエルの神なのです。
Ⅱ.ここに本当の解決がある(イザヤ7:10-14)
ところで、これは主が預言者を通して語られたことが成就するためであった、とありますが、それがどのような文脈で語られたのかを見ていきたいと思います。イザヤ7章14節をご覧ください。
「それゆえ、主は自ら、あなたがたに一つのしるしを与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。」
この預言が語られたのは前730年頃のことですが、その背景には、戦争という現実がありました。当時はアハズという王が南ユダ王国を治めていましたが、彼はアラムの王レツィンとエフライム、これは北イスラエル王国のことですが、その北イスラエルの王ペカが軍事同盟を結んで攻撃してくるという知らせを聞いたのです。とりわけアハズにとってショックだったのは、同胞の北イスラエルがアラムの王と手を組んだことでした。その知らせを聞いたアハズ王はどうなったかというと、「王の心も民の心も林の木々が風に揺らぐように揺らいだ」(イザヤ7:2)とあります。そんな動揺していたアハズの下に預言者イザヤが遣わされ、神からの言葉を伝えるのです。
「気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたは、これら二つの煙る木切れの燃えさし、アラムのレツィンとレマルヤの子の燃える怒りに、心を弱らせてはならない。」(イザヤ7:4)
「気を確かに持ち、落ち着いていなさい。心を弱らせてはならない。」これがその時アハズにとって一番必要なメッセージでした。とは言っても、このような状況で落ち着いていろという方が難しいかもしれません。しかしそれがどのような状況であったとしても、彼に求められていたことは、神の前に静まること、神がイスラエルの主であることを覚えることだったのです。
心を静めることのできないアハズに対して、イザヤは続けて神のことばを語ります。「それは起こらない。それはあり得ない」と。「それ」というのは、アラムとエフライムが攻めてくることです。それは起こらない。その上で神はアハズにこういうのです。
「あなたがたは、信じなければ堅く立つことはできない」(イザヤ7:9)
神の約束を信じること、それが堅く立つために必要なことでした。しかし、アハズは信じることができませんでした。これだけの励ましをもらっても、神を信じ切ることができなかったのです。
それはアハズに限ったことではありません。私たちもそういう時があります。私たちも神を信じています。そして、こうして神に祈ったり、礼拝したりしていますが、しかし、現実の生活の中で何らかの問題に直面すると、神を信じ切れない時があります。神に頼るのではなく、御言葉を信じるのでもなく、自分の思いのまま衝動的に動いてしまうことがあるわけです。現実に振り回され、信仰に堅く立つことができないのです。不安になった時、大きな問題に直面した時こそ、私たちはみことばに信頼し、神を信じなければならないのに、それができないという時があるのです。
そんなアハズ王に対して神はさらにイザヤを通して語られました。「あなたの神、主に、しるしを求めよ。」(イザヤ7:11) と。しかし、アハズは「私は求めません。主を試みません。」と言って、神のことばを明確に拒否しました。
そこで神は自ら彼に一つのしるしを与えられました。それがこのインマヌエル預言です。
「見よ。処女が身ごもっているそして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。」
つまり、これは神に対するアハズの信仰の結果として与えられたものではなく、逆にアハズの不信仰と不従順の結果、それにも関わらず神から与えられた神の恵みの約束だったのです。アハズがあくまでも自分の考えに従って行動していたので、神の方から一方的にそのしるしが与えられたのです。そのしるしとは何ですか。それは、処女が身ごもって、男の子を産み、その名を「インマヌエル」と呼ぶということでした。いったいこれは何のしるしなのか。この場合のしるしとは、神に信頼するなら守られるというしるしです。それが、処女がみごもって男の子を産み、その名を「インマヌエル」と呼ばれるようになるとうのはどういうことなのかさっぱりわかりません。
昔からこの箇所は非常に難解な箇所だと言われてきました。英国の有名な説教家チャールズ・スポルジョンは、この箇所は聖書の中でも最も難解な箇所の一つだと言いました。それほど解釈が難しい箇所なのです。何がそんなに難しいのかというと、ここに出てくる処女とはだれのことなのか、男の子とはだれのことなのかがはっきりわからないことです。それもそのはずです。処女がみごもるなんてことはあり得ないことだからです。そんな話今まで聞いたこともありません。ですから、これがしるしだと言われても、いまいち、ピンとこないわけです。
このことについて詳しく知りたい方は、以前私が礼拝でイザヤ書からお話した講解説教がホームページに載っていますのでそれを参考にしていただけたらと思いますが、確かなことは、これはこの時から約700年後に生まれるキリストのことを預言していたということです。どういうことかと言いますと、ここに本当の解決があるということです。アハズ王にとっては、確かにエフライム(北イスラエル)とアラムの連合軍が攻めてくるということは脅威だったでしょう。何とかしてそこから救われたいと、彼は北の大国アッシリヤに助けを求めました。それでアラムとエフライムは滅ぼされ問題は解決したかのように見えましたが、それは本当の解決ではありませんでした。本当の危機はその後でやって来ることになんです。昨日の友は今日の敵というようなことが起こるわけです。何と今度は自分たちがそのアッシリヤに攻められて苦しむことになるのです。ですから、それは本当の解決ではありませんでした。本当の解決はどこにありますか。本当の解決はここにあります。インマヌエルと呼ばれるお方です。すなわち、イエス・キリストにあるのです。これが、神が与えてくださったしるしだったのです。
いったいなぜ神がともにおられるということが本当の解決なのでしょうか?なぜなら、神はキリストにおいてアラムやエフライムの連合軍やアッシリヤによる攻撃から救われるといったところではない、永遠の滅びに追いやろうとするサタンの攻撃、すべての悪の根源である罪から救ってくださるからです。このイエスが私たちの罪のために十字架にかかって死なれ、三日目によみがえられることによって、神はこの救いの御業を成し遂げてくださいました。永遠の滅びから、永遠の救いの中へと、すなわち、永遠に神が私たちと共におられるという約束の中へ私たちを導いてくださったのです。ですから、イエス様は私たちのどのような問題や苦しみからも救うことがおできになるのです。これが本当の解決であり、救いなのです。これがクリスマスに実現したのです。
Ⅲ.インマヌエルの実現のために(マタイ1:24-25)
ですから第三のことは、あなたを罪から救うために生まれてくださった救い主イエスをあなたの心に受け入れてくださいということです。そのとき、このインマヌエルの預言があなたに成就することになります。マタイの福音書に戻りましょう。1章24~25節をご覧ください。
「24ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じたとおりにし、自分の妻を迎え入れたが、25 子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そして、その子の名をイエスとつけた。」
ヨセフは眠りから覚めたとき、主の使いが命じられたとおりに、マリアを自分の妻として迎え入れました。起きて思い巡らしているだけではもがき苦しむだけでしたが、眠りと夢の中で神が働いてくださり、彼を新しく造り変えられました。それで彼は神のご計画に身をゆだねることができたのです。ここにインマヌエルの約束と祝福に生きるヨセフが誕生しました。
それはヨセフだけではありません。あなたも神の御言葉に信頼し、あなたを罪から救うためにお生まれになられたイエスを信じるなら、あなたにもインマヌエル、神はあなたとともにおられるという御言葉が実現します。それはイエスを信じた時だけではありません。いつも、いつまでも、ともにいてくださいます。
マタイの福音書を見ると、この1章で「神は私たちとともにおられる」と約束してくださった主は、その最後の28章でも共におられると約束しておられます。28章20節です。
「見よ。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたとともにいます。」
そればかりではありません。その真ん中にもこの約束が出てきます。18章20節です。
「二人か三人がわたしの名において集まっているところには、わたしもその中にいるのです。」」
つまり、インマヌエルとして生まれ手くださった方は世の終わりまでいつまでも共にいてくださるだけでなく、この地上の生涯を歩む時も共にいて支え、励ましてくださるのです。
であれば、何を恐れる必要があるでしょうか。その名は「インマヌエル」と呼ばれるお方はいつもあなたとともにいて、あなたを助け、あなたを守ってくださいます。これが本当の救いです。インマヌエルという名でこの世に来られた方は、遠くから私たちの苦しみを眺めておられる方ではなく、いつもあなたとともにいて自らが先頭に立ち、罪と死に真正面から戦ってくださるお方なのです。
あなたが心配しておられることは何ですか。何を恐れていらっしゃいますか。ひとりぼっちで孤独を感じておられますか。自分や家族の病気で不安な日々を過ごしておられますか。将来に何の希望もないと絶望しておられますか。でも、主はあなたのために生まれてくださいました。あなたは一人ぼっちじゃないのです。主があなたとともにおられます。どんなことがあってもあなたを見捨てることはありません。世の終わりまで、いつもあなたとともにおられます。この方に信頼しましょう。クリスマスに与えられる喜びは、まことに私たちのために与えられた救いの恵みです。それは神があなたとともにおられるという約束です。この神に信頼して、この地上の生涯を全うさせていただきましょう。
最後に、ロバート・コリアー著、「冬の嵐の中の小鳥の歌」から抜粋した詩を引用して終わります。
信頼
わたしは一度 神を信頼したのだから
いつまでも 神を信頼する
わたしが立とうが 倒れようが、その道は最善
風と嵐の中に、主は決して わたしを捨て置かれない
神はすべてを 送ってくださるのだ
風と嵐の中に、主は決して、あなたを捨て置くことはなさいません。いつもともにいて、あなたを最善に導いてくださいます。この神に信頼しましょう。メリー・クリスマス!主の恵みと平安が、あなたとともにありますように。
思いがけない神の助け エレミヤ書38章1~28節
聖書箇所:エレミヤ書38章1~28節(旧約P1364、エレミヤ書講解説教68回目)
タイトル:「思いがけない神の助け」
今日は少し長いですが、エレミヤ書38章全体からお話します。タイトルは「思いがけない神の助け」です。この38章も、南ユダ最後の王ゼデキヤの時の出来事です。時は前586年に南ユダ王国が滅ぼされる直前です。前の章では、エレミヤがエルサレムから出てベニヤミンの地に行ったとき、ベニヤミンの門のところでイルイヤという名の当直の者に捕らえられ、書記ヨナタンの家の牢屋に投獄されたことを見ました。そこは丸天井の地下牢で、エレミヤは長い間そこにいました。
今日の箇所にも、エレミヤが再び捕らえら投獄されることが記されてあります。エレミヤが投獄されるのは、これが3回目です。しかし、今回の投獄はこれまで以上に過酷なものでした。というのは、命の危険が脅かされるほどのものだったからです。しかし、そのような中にあっても神は思いがけない方法で彼を救い出されます。神はどんなことがあっても、神を恐れ、神に信頼して歩む者を、救い出してくださいます。それゆえ私たちは、私たちの人生においてどんなことが起こっても、ただ神を愛し、神のことばに信頼して歩まなければなりません。
Ⅰ.投獄されたエレミヤ(1-6)
まず1~6節をご覧ください。「1 さて、マタンの子シェファテヤと、パシュフルの子ゲダルヤと、シェレムヤの子ユカルと、マルキヤの子パシュフルは、エレミヤが民全体に次のように語ることばを聞いた。2 「【主】はこう言われる。『この都にとどまる者は、剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。そのいのちは戦勝品として彼のものになり、彼は生きる。』3 【主】はこう言われる。『この都は、必ず、バビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。』」4 そこで、首長たちは王に言った。「どうか、あの男を死刑にしてください。彼はこのように、こんなことばを皆に語り、この都に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。実にあの男は、この民のために、平安ではなくわざわいを求めているのです。」5 するとゼデキヤ王は言った。「見よ、彼はあなたがたの手の中にある。王は、あなたがたに逆らっては何もできない。」6 そこで彼らはエレミヤを捕らえ、監視の庭にある王子マルキヤの穴に投げ込んだ。彼らはエレミヤを綱で降ろしたが、穴の中には水がなく、あるのは泥だったので、エレミヤは泥の中に沈んだ。」
1節には、南ユダ最後の王ゼデキヤの4人の側近者の名前が記されてあります。このうちパシュフルは21章1節に、ユカルも37章3節に出てきました。彼らはエレミヤが民全体に語ることを聞いて腹を立て、ゼデキヤ王のところへ行って不満を申し立てました。なぜなら、エレミヤがエルサレムにとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところ、すなわち、バビロンに出て行く者は生きると語っていたからです。そんなことを聞いたらエルサレムに残っている戦士や民全体の士気がくじかれると思ったのです。彼らの目では、エレミヤは民のために平安を語っているのではなくわざわいを語っているように見えました。
それで、ゼデキヤ王はどうしたかというと、首長たちの言うことを受け入れ、彼らの思いのままにして良いと告げました。それで彼らはエレミヤを捕らえると、監視の庭にある王子マルキヤの穴の中に投げ込みました。先ほども申し上げたように、エレミヤが投獄されるのはこれが3回目です。前回は37章16節で見ましたが、今回のそれはもっと過酷なものでした。というのは、命の危険が脅かされるどのものだったからです。そこには大量の泥があって、その中に沈んでいくような状態だったのです。
皆さん、私たちにもそのような時があるのではないでしょうか。私は先週目決めの手術で入院していましたが、それはある意味で泥の中に沈んでいくようなものでした。11月15日に最初の手術をしましたが多量の出血があり、それが目の奥の硝子体というところまで入り込んでしまったため、凍った車のフロントガラスのように全く見えなくなってしまいました。かなり焦りました。このまま失明してしまうのではないかと思うと、いてもたってもいられなくなり、私はしぼんだ風船のようになってしまいました。す。結局、5日目に2度目に硝子体の中の出血を取り除く手術をしました。幸い視力はある程度回復することができましたが、今度は逆に眼圧が低くなりすぎて見づらくなってしまいました。あまり色々なものを見るなという神様からのメッセージなのかもしれませんが、まだ本調子ではありませんが、神様がエレミヤを泥から引き上げたように、私の目も眼圧から引き上げてくださると信じています。
でもそれは私だけのことではないでしょう。だれでも泥の中に沈むような時があります。それはエレミヤのように敵から攻撃された時や、私のような病気になる時もそうですが、夫婦の問題や家族の問題で悩むとき、仕事上のトラブルや人間関係の問題が起こる時もそうでしょう。経済的に苦しくて借金を抱えてしまったという時もそうです。最愛の人を失った時もそうです。その悲しみから立ち上がるには相当の時間がかかります。私たちの人生には、泥の中に沈んでしまうような時があるのです。でもどんなに沈んでも、神様は必ずあなたをそこから引き上げてくださるということを忘れないでください。しかも、あなたが想像することができないような不思議な方法で助けてくださる。そこには思いがけない神の助けがあるのです。
Ⅱ.思いがけない神の助け(7-13)
では、エレミヤはどのようにしてその中から救い出されたのでしょうか。7~13節をご覧ください。「7 王宮にいたクシュ人の宦官エベデ・メレクは、エレミヤが穴に入れられたことを聞いた。また、そのとき王はベニヤミンの門のところに座っていたので、8 エベデ・メレクは王宮から出て行き、王に告げた。9 「わが主君、王よ。あの人たちが預言者エレミヤにしたことは、みな悪いことばかりです。彼らはあの人を穴に投げ込みました。もう都にパンはありませんので、あの人はそこで飢え死にするでしょう。」10 すると王は、クシュ人エベデ・メレクに命じた。「あなたはここから三十人を連れて行き、預言者エレミヤを、まだ死なないうちに、その穴から引き上げなさい。」11 エベデ・メレクは人々を率いて、王宮の宝物倉の下に行き、そこから着古した衣服やぼろ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミヤのところに降ろした。12 クシュ人エベデ・メレクはエレミヤに、「さあ、古着やぼろ切れをあなたの脇の下の綱に当てなさい」と言ったので、エレミヤがそのとおりにすると、13 彼らはエレミヤを綱で穴から引き上げた。こうして、エレミヤは監視の庭にとどまった。」
エレミヤが泥の中に沈んだとき、主は王宮にいたクシュ人の宦官エベデ・メレクという人物を用いて救い出されました。クシュ人とはエチオピア人のことです。すなわち異邦人ですね。また、宦官とは、去勢を施された人、陰茎を切り取られた人のことです。モーセの律法によれば、このような人は主の集会に加わってはならないと定められていました。申命記23章1節にこうあります。「睾丸のつぶれた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。」神様はこの異邦人エベデ・メレクを用いてくださいました。彼はそういう立場でありながら、エレミヤが穴に入れられたと聞くと王宮から出て行き、王のところに行って、首長たちの悪行とエレミヤの窮状を訴えたのです。
するとゼデキヤ王は、クシュ人エベデ・メレクの訴えに同意し、彼に、30人を連れてエレミヤのところに行き、彼がまだ死なないうちに、その穴から引き上げるようにと命じました。エベデ・メレクは、ゼデキヤ王の命令に従い、人々を率いて、王宮の宝物倉の下に行き、そこから着古した衣服やぼろ切れを取り、それらを綱にして穴の中にいたエレミヤのところに降ろし、彼を穴から引き上げたのです。こうしてエレミヤは監視の庭にとどまることができました。
だれがそのようなことを考えることができたでしょうか。彼はエレミヤを迫害していたユダの首長たちとは対照的でした。彼は自分に降りかかる危険をかえりみず王の所へ行くと、王の面前で首長たちの誤りを指摘し、エレミヤに助けの手を差し伸べたのです。神様はこのように、時に私たちの想像を超えた方法や思いがけない人を用いて私たちを助けてくださるのです。詩篇121篇にこうあります。
「1 私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。
2 私の助けは【主】から来る。天地を造られたお方から。
3 主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。
4 見よ イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。
5 【主】はあなたを守る方。【主】はあなたの右手をおおう陰。
6 昼も日があなたを打つことはなく夜も月があなたを打つことはない。
7 【主】はすべてのわざわいからあなたを守り、あなたのたましいを守られる。
8 【主】はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。」
皆さん、私たちの助けはどこから来るのでしょうか。私たちの助けは天地を造られた主から来ます。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともありません。主はすべてのわざわいからあなたを守り、あなたのたましいを守られます。今よりとこしえまでも守られる。あなたが困難に陥った時、自分でもどうしたら良いかわからないような時でも、主は必ずあなたをそこから助け出してくださるのです。それはあなたが思い描く方法によってではなく、それをはるかに超えた方法によって成し遂げてくださいます。そのような恵みを、私たちはしばしば体験することがあります。
私がかつて福島で教会開拓をしていた時、開拓して10年目に会堂建設に取り組みました。多くの人々が救いに導かれ自宅の集会スペースに入れなくなった時、もっと広い土地を求めて祈りました。そして与えられたのがそこから歩いて10分のところにある広々とした土地でした。そこは600坪もありました。しかも交通のアクセスもよく、教会の会堂を建設するのにはとても良い土地でした。ところがそこは調整区域に定められていて、建物が建てられてない場所になっていました。そういう土地に教会を建てたという前例は、福島県ではそれまで一度もありませんでした。でも神様のみこころなら必ず与えられると信じて、開発許可の取得に取りかかりました。
そのためにはまずしなければならなかったのは、宗教法人を取得することです。しかし教会名義の土地、建物がなかったので、そのために自分の名義の土地と建物を教会の名義にしようとしましたが、そのためには銀行から借り入れた際の抵当権を抹消しなければなりませんでした。抵当権を抹消するということは、その代わりに保証人として立てなければならないということですが、そのような人は教会にはいませんでした。いたとしてもそれはかなり荷が重すぎる話です。ですから、その作業は暗唱に乗り上げてしまいました。
ところが、ちょうどその頃、多くの青年たちが救いに導かれていましたが、その中に市内で老舗の洋服店を営んでいるクリスチャンの御夫妻の娘さんが救われたのです。また、その2人の兄弟も教会に導かれ、熱心に神様を求めるようになりました。驚いたのはその御両親です。どうやって彼らがそのように変えられたのか知りたいと、お母さんが「私にも聖書を教えてください」と言ってこられたのです。7回の学びが終わったとき、そのお母さんがこう言われました。
「本当にありがとうございました。よくわかったような気がします。子どもたちがあんなに喜んで教会に行っていくようになったのかも。私には何もできませんが、もし何かお役に立てることがありましたら何でも教えてください。」
と言われかえって行かれました。
すると、隣にいた家内が私の顔を見てこう言いました。「あなた、もしかするとあのことをお願いしてみたらどうですか。」家内はこういう時に勘が鋭いんですね。でも私はまさかそんなことお願いできないと思いましたが、でも一応お願いしてみることにしました。
すると、後日ご主人から電話がかかってきて、その件についてお話したいのでお店まで来ていただけませんかと言われました。お店に行ってみると、ご主人からこう言われました。
「先生、家は先祖代々人様の保証人にはならないと決めているんです。でも、今回は違います。今回は人様ではなく神様の保証人です。だから喜んで引き受けさせていただきます。」
私はびっくりしました。いくら教会のこととはいえ、誰が保証人になりたいと思うでしょうか。私はそのように導いてくださった神様に心から感謝しました。そして、今からちょうど30年前の1994年11月に宗教法人が認可され、その3年後に、これも本当に不思議な導きでしたが調整区域の開発許可が認可され、その翌年に新会堂を主に献げることができたのです。これがその会堂です。
まさかそのような形で会堂建設が進んでいくなんて誰も考えることができなかったと思います。でも、神様にとって不可能なことは一つもありません。神にはどんなことでもできるのです。まさにあのヨブが最後に告白したように、「あなたには、すべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。」(ヨブ42:2)ということを、私も知りました。それが神のみこころならば、神はあらゆる方法を通してそれを成し遂げてくださいます。私たちが想像することもできないような思わぬ方法で助けてくださるのです。
それはエレミヤが例外だったからではありません。エレミヤの時に働かれた神は、今も生きて働いておられ、あなたの思いを越え、あなたが考えられない方法で、あなたを穴から引き上げてくださるのです。ですから、あなたがどんな穴に投げ込まれたとしてもがっかりしないでください。どんなに泥の中に沈んでいるようでも恐れないでください。主はあなたに思いがけない助けを与えてくださいますから。まさにあなたが夢を見ているような方法であなたを助けてくださるのです。
Ⅲ.ただ神に信頼して(14-28)
ですから第三のことは、ただ神に信頼しましょう、ということです。14~28節をご覧ください。19節までをお読みします。「14 ゼデキヤ王は人を送って、預言者エレミヤを自分のところ、【主】の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミヤに、「私はあなたに一言尋ねる。私に何も隠してはならない」と言うと、15 エレミヤはゼデキヤに言った。「もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すのではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞かないでしょう。」16 そこでゼデキヤ王は、ひそかにエレミヤに誓った。「私たちの、このいのちを造られた【主】は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。また、あなたのいのちを狙うあの者たちの手に、あなたを渡すことも絶対にしない。」17 すると、エレミヤはゼデキヤに言った。「イスラエルの神、万軍の神、【主】はこう言われる。『もし、あなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたのたましいは生きながらえ、この都も火で焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる。18 あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることができない。』」19 しかし、ゼデキヤ王はエレミヤに言った。「私は、カルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶりものにするのではないか、と。」
ゼデキヤは人を送って、エレミヤを自分のところに召し寄せました。そして彼に一言求めました。何も隠してはならないと。するとエレミヤは、もし自分が告げれば、あなたは必ず私を殺すのではないかと答えると、ゼデキヤは、絶対に殺さないとひそかに誓ったので、エレミヤはゼデキヤにはっきりと主のことばを告げました。すなわち、もし彼がバビロンの王に降伏するなら彼は生きながらえ、彼の家族も、エルサレムも火で焼かれることはないが、もしバビロンの王に降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、彼自身も彼らに渡され、殺されることになるということです。もう何度も語られてきたことです。それなのになぜゼデキヤは再びエレミヤに尋ねたのでしょうか。
おそらくゼデキヤは、今までとは違ったことをエレミヤが言うのではないかと期待していたからです。しかし、エレミヤがゼデキヤに告げた言葉はこれまでと全く同じことでした。エレミヤはどこまでも、神の預言者として神に対して忠実だったのです。
それに対してゼデキヤはどうかというと、いつも人を恐れていました。19節には、「私は、カルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶりものにするのではないか、と。」あります。彼が恐れていたのは敵のバビロン軍が攻めてくるということよりも、エレミヤの語る神のことばに従ってバビロンに降伏して捕囚の民として連れて行かれたユダヤ人たちになぶりものにされるということでした。ですから、彼はひそかにエレミヤに尋ねたのです。本当の敵は外側よりも内側にいることがあるのです。
しかし、優柔不断な性格のゼデキヤはなかなか決断することができませんでした。それはゼデキヤだけではないでしょう。私たちもそういう時があります。それが神のみこころだとわかっていても、なかなか神に従うことができないことがあります。なぜでしょうか?人を恐れるからです。そんなことをしたらあの人に迷惑がかかるのではないか。この人から何を言われるかわからない。もしかすると、自分の立場が危うくなるかもしれない。その結果、生活にも影響を及ぼすことになるかもしれない。そう思うと、決断することができないのです。しかし、箴言に「人を恐れるとわなにかかる。 しかし主に信頼する者は守られる。」(箴言29:15)とあるように、人を恐れると、必ず失望することになります。私たちが恐れなければならないのは、私たちが信頼しなければならないのは、いつまでも変わることのない神とそのことばだけです。
イギリスで最も多くの会衆を牧会していたと言われている伝道者のチャールズ・スポルジョンは、ゼデキヤ王のようにためらっている会衆に次のように説教しました。「皆さん、いつまでためらっているのですか。皆さんは、うわべは宗教的ですが実はまだこの世の人なのです。ですから、今でもどっち側に立つべきかわからない」と言ってためらっているのです。いつまでも2つの間でもじもじしないでください。「次の機会が来れば悔い改める」と言って、人生の砂時計の砂をただ見送らないでください。皆さんが「砂がほとんど落ちたら、神のもとへ向かおう」と言う時はもう遅いのです。皆さんは、神とこの世の2つの間を行ったり来たりしながらも、神を信じていると言います。しかし、それは神を信じているということではありません。神を信じるとは、「ただ神だけを」信じることを言うのですと。
あなたはどうですか。あなたはためらっていませんか。神を信じていると言いながらも手放せないでいるものはありませんか。神だけに拠り頼むためにあなたが捨てるべきものは何ですか。あなたはだれを恐れて日々決断をしているでしょうか。ただ神だけを恐れ、神に立ち返りましょう。
最後に24~28節をご覧ください。「24 ゼデキヤはエレミヤに言った。「だれにも、これらのことを知らせてはならない。そうすれば、あなたは死なない。25 もし、あの首長たちが、私があなたと話したことを聞いてあなたのところに来て、『さあ、何を王と話したのか、教えろ。隠すな。あなたを殺しはしない。王はあなたに何を話したのか』と言っても、26 あなたは彼らに、『王がヨナタンの家に私を返し、そこで私が死ぬことのないようにと、王の前に嘆願をしていた』と言いなさい。」27 首長たちがみなエレミヤのところに来て、彼に尋ねたとき、彼は、王が命じたことばのとおりに彼らに告げたので、彼らは彼と話すのをやめた。あのことは、だれにも聞かれていなかったのである。28 エレミヤは、エルサレムが攻め取られる日まで、監視の庭にとどまっていた。エルサレムが攻め取られた次第は次のとおりである。ゼデキヤはエレミヤに言った。」
ゼデキヤ王はエレミヤに、このことをだれにも知らせてはならないと命じました。もし話せば、首長たちはエレミヤを殺すかもしれないからです。それでエレミヤは、首長たちが彼のところにやって来て、何を王と話していたのかと尋ねたとき、王が命じたとおりに、王がヨナタンの家に私を返し、そこで私が死ぬことがないようにと、王の前に嘆願していたと告げると、彼らはエレミヤと話すのをやめました。このゼデキヤ王の提言は、エレミヤのためというよりも、むしろ自分自身のためでした。エレミヤは自分の職務にいのちをかけていたことをゼデキヤ王は知っていたからです。そのエレミヤと隠れた取引をしたと思われることを、ゼデキヤ王は恐れたのです。結局、彼はエレミヤを通して語られた神のことばを聞きながら、それに従うことができませんでした。
皆さん、神の御心を知ってもそれを行うかどうかはまた別の問題です。聞くことと行うこととの間には固い決断が求められるからです。ゼデキヤは、神のことばを真剣に聞きましたが、それを首長たちに伝える勇気がありませんでした。また、彼らに伝えた時にエレミヤに降りかかる危険を防ぐ力もありませんでした。門の外では、王とエレミヤとの間でどのような話が交わされたのか、関心を持っていた首長たちがいましたが、ゼデキヤは、何事もなかったかのように装いました。南ユダ王国の運命がかかった重要な密談が、特に内容のない私的な会話とされたのです。その結果、個人的な危機は逃れましたが、南ユダ王国の運命は終わることになってしまいました。大切なのは、御言葉を聞くだけで終わらないということです。御言葉を聞いたなら、それを実行に移さなければなりません。
イエス様はみことばを聞いてそれを行う人は、岩の上に家を建てた賢い人にたとえることができると言われました。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。しかし、みことばを聞いてもそれを行わない人は、砂の上に自分の家を建てた愚かな人にたとえることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいます。皆さん、神のことばを聞いて、それを行う、岩の上に自分の家を建てる人になりましょう。そうすれば、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、倒れることはありません。
あなたにとって神の御言葉を聞いても実行することができないでいることは何ですか。今、それを神に明け渡しましょう。それはあなたの力でできることではありません。そのためには神の恵みと神の力が必要です。そしてそのために神はひとり子イエスをあなたに与えてくださいました。神はあなたの罪の身代わりとしてイエス様を十字架に付けてくださることによって、あなたの罪を完全に清めてくださいました。あなたはそれほど神に愛されているのです。神の恵みはあなたに十分注がれています。この神の愛と恵みを受け取るとき、あなたにも神の愛が満ち溢れ、あなたのすべてを神に献げることができるようになります。それはちょうど船の上から一歩踏み出すようなものです。イエス様なしでは、沈んでしまう水の上に踏み出すようなものなのです。でも、この弱いこの足に神が力を与えてくださるとき、神のみことばの上を歩むことができるようになります。たとえ嵐の中でも、ただ御顔を見つめ、イエス様あなたと共に歩みますと、一歩踏み出すことができるようになる。そこに神の思わぬ助けがあることを信じて、あなたもその一歩を踏み出してください。
ただ神を恐れて エレミヤ37章1~21節
前回は36章から、エホヤキムが神のことばを暖炉の火で焼き尽くしたという出来事を通して、神のことばは絶対に滅びることはないということを学びました。今回は37章全体から、南ユダの王ゼデキヤと預言者エレミヤの生き方から、「ただ神を恐れて」というタイトルでお話します。
Ⅰ.ゼデキヤ王の祈り(1-10)
まず1~10節をご覧ください。「1 ヨシヤの子ゼデキヤは、エホヤキムの子エコンヤに代わって王となった。バビロンの王ネブカドネツァルが彼をユダの地の王にしたのである。2 彼も、その家来たちも、民衆も、預言者エレミヤによって語られた【主】のことばに聞き従わなかった。:3 ゼデキヤ王は、シェレムヤの子ユカルと、マアセヤの子、祭司ゼパニヤを預言者エレミヤのもとに遣わして言った。「どうか、私たちのために、私たちの神、【主】に祈ってください。」:4 エレミヤは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられてはいなかった。5 また、ちょうど、ファラオの軍勢がエジプトから出て来たので、エルサレムを包囲中のカルデア人は、そのうわさを聞いて、エルサレムから引き揚げたときであった。6 そのとき、預言者エレミヤに次のような【主】のことばがあった。7 「イスラエルの神、【主】はこう言われる。わたしに尋ねるために、あなたがたをわたしのもとに遣わしたユダの王にこう言え。『見よ。あなたがたを助けに出て来たファラオの軍勢は、彼らの地エジプトへ帰り、8 カルデア人が引き返して来て、この都を攻め取り、これを火で焼く。9 【主】はこう言われる。あなたがたは、カルデア人は必ず私たちのところから去る、と言って、自らを欺くな。彼らが去ることはないからだ。10 たとえ、あなたがたが、あなたがたを攻めるカルデアの全軍勢を討ち、そのうちに重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らはそれぞれ、その天幕で立ち上がり、この都を火で焼くようになる。』」」
ヨシヤの子ゼデキヤは、エホヤキムの子エコンヤに代わって南ユダの王となりました。彼は南ユダ最後の王となります。この後でエルサレムはバビロンによって完全に陥落することになります。彼もバビロンに連れて行かれ、そこで死を迎えることになりますが、その最後の王がこのゼデキヤです。彼は正統的な王位継承者ではありませんでした。エホヤキムの子エコンヤが在位わずか3か月でバビロンに捕え移されたので、彼に代わってユダを治めさせるためにバビロンの王によって擁立されたのです。いわゆるバビロンによって任命された操り人形、傀儡(かいらい)王(おう)にすぎなかったわけです。彼がユダを治めていた時代がどのようなものであったかは、2節に総括されています。ご一緒に読みましょう。
「彼も、その家来たちも、民衆も、預言者エレミヤによって語られた主のことばに聞き従わなかった。」
ゼデキヤ王がユダを治めていた間は、彼も、その家来たちも、民衆も、誰も、預言者エレミヤによって語られた主のことばに聞き従いませんでした。どういう点で彼らは聞き従わなかったのでしょうか。それは、エレミヤが語る神のことばを受け入れなかったという点においてです。エレミヤはゼデキヤ王をはじめその家来たちや民衆に、バビロンに降伏することが神のみこころであると語ったのに、彼らはその言葉に従わず、自分を王に立てたバビロンの王ネブカドネツァルに反旗を翻したのです。彼らはどのようにバビロンに逆らったのでしょうか。この後のところを読むとわかりますが、この時エジプトのフェラオの軍勢がエジプトを出て来てバビロン軍と戦おうとしていましたが、彼らの中にはそのエジプトと手を結んでバビロンを倒すようにとゼデキヤに圧力をかける者たちがいたのです。実際、エジプト軍はバビロンに対抗するためにユダをはじめパレスチナ諸国に同盟を呼び掛けていました。そのような呼び掛けに応じて、ゼデキヤはついにバビロンに反旗を翻したのです。それなのに彼は3節でエレミヤのもとに使いを遣わしてこう言いました。
「どうか、私たちのために、私たちの神、主に祈ってください。」
どういうことでしょうか。日頃、エレミヤのことばには耳を貸そうともしていなかったのに、バビロン軍がエルサレムを包囲すると、溺れる者、藁を掴むで、苦しい時の神頼みに走ったのです。しかし、それはあまりにも身勝手な要求でした。日頃、神のことばに従がおうとしないで自分勝手な生活をしていながら、自分にとって都合が悪くなると、神様、助けてくださいと祈るのはあまりにも虫のいい話だからです。確かに「私のために祈ってください」と願うこと自体は悪いことではありません。それはへりくだっていなければできないことだからです。私は長い間、なかなかそのように言うことができません。自分で何とかすると思っていたからです。しかし、度重なる病を通して、また、個人的な問題を通して自分にはもう無理だとギブアップしたとき、心から「私のために祈ってください」と言えるようになりました。ですから、今は少しへりくだっているのです。まあ、こういうふうに言うこと自体高慢なんですけれども。ですから、祈ってくださいとお願いすること自体は問題ではないのですが、もっと大切なことがあるのです。それは神様との関係です。神様とどのような関係を持っているのかということです。神のことばに留まっているかどうかということです。それに聞き従っているかどうかということです。主イエスはこう言われました。
「あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それはかなえられます。」(ヨハネ15:7)
私たちの祈りが聞かれる条件は何ですか。どうすれば祈りが聞かれるのでしょうか。あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまっているなら、です。そうすれば、神はそれをかなえてくださいます。そうでないのに、ただ苦いし時の神頼みのように祈っても、神は聞いてくださることはありません。なぜなら、神はうわべを見られるのではなく、心を見られるからです。ヘブル11章6節にはこうあります。
「信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。」
信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるということを、信じなければなりません。あなたの人生において何らかの問題を抱えた時だけでなく、あるいは危機に陥った時だけでなく、どんな時でも神がおられることと、神を求める者には報いてくださるということを信じなければなりません。つまり、神を信じ、神を愛し、神のことばに従い、神のみこころに生きるということが求められているのです。今、ディボーションで箴言を呼んでいますが、箴言の言葉で言うなら、神の知恵を求めるということです。神の知恵とは何ですか。それは、神を恐れることです。箴言1章7節にこうあります。
「主を恐れることは知恵の初め。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。」
主を恐れることが知恵の初めです。その教えを受け入れ、その命令を私たちのうちに蓄え、それに従って生きること。これが神の知恵です。それがなければどんなに祈ったとしても、その祈りが聞かれることはありません。
ゼデキヤはどうでしたか。彼は預言者エレミヤによって語られた主のことばに聞き従いませんでした。それなのに彼は祭司ゼパニヤをエレミヤのもとに遣わして、「どうか、私たちのために、私たちの神、主に祈ってください。」と懇願しました。そのような祈りが聞かれるはずがありません。あまりにも虫のいい話です。彼の信仰はどちらかというと他人任せでした。自分から神の前に出ることもしませんでした。いや、できなかったのでしょう。神のことばに従っていませんでしたから。神様に顔向けできるような心境ではなかったのでしょう。だから、だれか他の人に祈ってもらうことによってそれを叶えようと思ったのです。そういうことが私たちにもあります。自分のような者が祈っても神様は聞いてくれないから、牧師さん、祈ってもらえませんか・・・。言われた方も大変です。誰が祈っても同じだからです。問題は誰が祈るかということではなく、祈るその人が神を信じ、神を愛し、神のことばに従い、へりくだって神の前に出ているかどうかです。もしその人が神を信じ、へりくだって神を愛し、神に従っているなら、神は必ず聞いてくださいます。大切なのは、神に祈るという行為とか形ではなく、神を愛し、神に従っているかどうかという中身なのです。神との関係です。その上でもし神に従っていないということが示されたなら、悔い改めて神に立ち返らなければなりません。そうすれば、神はあなた罪を赦し、すべての悪からあなたをきよめてくださいます。その時あなたは神の愛と赦しを受け取り、神との関係を回復することができます。あなたがどんな罪を犯したとしても。その上で祈らなければなりません。それが聖書があなたに約束していることです。それが十字架と復活の御業を通して主イエスが成し遂げてくださったことです。
「永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。それゆえ、わたしはあなたに真実の愛を尽くし続けた。」(エレミヤ31:3)
あなたはこの神の愛と赦しを受け取りましたか。永遠の愛をもって神はあなたを愛してくださいました。真実の愛を尽くし続けてくださいました。ですから、この愛を受け取り、悔い改めて神に立ち返ってください。そして神のことばに聞き従ってください。そうすれば、神は必ずあなたの祈りを聞いてくださいます。新約聖書のヤコブ書にはこうあります。
「ですから、あなたがたは、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。いやされるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。」(ヤコブ5:16、第三版)
義人の祈りは働くと、大きな力があります。義人とはどういう人ですか。義人とは清く、正しく、美しい人のことではありません。また、良い行いをしている立派な人でもありません。義人とは互いに自分の罪を言い表し、神の赦しと救いを受け入れた人のことです。すなわち、自分の罪を悔い改め、救い主イエス・キリストを信じ、神のことばに従って生きている人のことです。そのような義人の祈りは働くと、大きな力があるのです。
ゼデキヤはそうではありませんでした。彼は神のことばにとどまっていませんでした。それなのに彼は、「私たちのために、私たちの神に祈ってください。」と言いました。そのような祈りが聞かれることはありません。
このゼデキヤ王の約100年前にヒゼキヤという王がいましたが、これがヒゼキヤと決定的に違う点でした。ゼデキヤとヒゼキヤでは名前はとてもよく似ていますが、中身は全く違います。ヒゼキヤの時代はバビロンではなくアッシリアという国がエルサレムを包囲するという同じような状況下に置かれましたが、彼はゼデキヤと違いどんなに敵に脅されても屈することをしませんでした。そして、自分の衣を引き裂き粗布を身にまとって主の宮に入って行くと、主の前に祈りました。これは深い悔い改めを表す行為です。そして、当時の預言者であったイザヤにとりなしの祈りを要請したのです(Ⅱ列王18:13)。するとどのような結果になったでしょうか。イザヤは神からのことばを彼に伝えました。Ⅱ列王19章6~7節です。
「6 イザヤは彼らに言った。「あなたがたの主君にこう言いなさい。『【主】はこう言われる。あなたが聞いたあのことば、アッシリアの王の若い者たちがわたしをののしった、あのことばを恐れるな。7 今、わたしは彼のうちに霊を置く。彼は、あるうわさを聞いて、自分の国に引き揚げる。わたしはその国で彼を剣で倒す。』」
そのことばの通り、その夜の内に主の使いがアッシリア軍を撃ち、アッシリアの陣営で18万5千人を打ち殺しました。つまり、彼の祈りは聞かれたのです。だれがこのようなことを想像することができたでしょうか。これが主のなさることです。主はへりくだって主の前に悔い改め、主に信頼し、主に従う者を決して蔑(ないがし)ろにすることはなさいません。私たちの思いをはるかに超えて、ご自分の愛する者ために働いて御業を成してくださるのです。
しかし、ゼデキヤ王はそうではありませんでした。彼はこのようになることを期待していたのでしょうが、事態はそのようには動きませんでした。ユダを助けるためにエジプトから出て来たファラオの軍勢によってバビロン軍は一時的にエルサレムから引き揚げるが、その後引き返して来て、この都を攻め取り、これを火で焼くようになる、と言われました。ゼデキヤの祈りは聞かれなかったのです。ヒゼキヤは神を恐れ、神に信頼し、へりくだって神のことばに聞き従ったのに対して、ゼデキヤはあくまでも自分の考えや思いを優先して、神のことばには聞き従わなかったからです。
すべてのことは神のみこころにかかっているのです。虚しい望みにすがって自らを欺いてはなりません。自分の思いを優先すれば、結局滅んでしまうことになります。大切なのは、自分の思いではなく、神のみこころに従うことです。それは神のことばである聖書に従って生きることです。そうすれば、神はあなたの祈りを聞いてくださり、あなたに神の御業を現わしてくださるのです。
「何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。」(Ⅰヨハネ5:14)
あなたは自分の思い通り、期待通りになることを願って、ひどく失望したことはありませんか。期待することは大切なことですが、もっと大切なことは、神に従うことです。神との関係です。それが神のみこころにかなう願いなのかどうかということです。今、神のみこころに従わせるべきあなたの思い、あなたの期待は何ですか。困難の中で、ゼデキヤのように自分の思いが優先することがないように、まず神の国と神の義を第一に求めましょう。それが、私たちが祈りをささげるときに持つべき心なのです。
Ⅱ.たとえ誤解されても(11-16)
次に、11~16節をご覧ください。「11 カルデアの軍勢がファラオの軍勢のゆえにエルサレムから引き揚げたとき、12 エレミヤは、エルサレムから出て行き、ベニヤミンの地に行った。民の間で割り当ての地を受け取るためであった。13 彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナンヤの子シェレムヤの子の、イルイヤという名の当直の者がいて、「あなたはカルデア人のところへ落ちのびるのか」と言い、預言者エレミヤを捕らえた。14 エレミヤは、「違う。私はカルデア人のところに落ちのびるのではない」と言ったが、イルイヤは聞かず、エレミヤを捕らえて、首長たちのところに連れて行った。15 首長たちはエレミヤに向かって激しく怒り、彼を打ちたたき、こうして書記ヨナタンの家の牢屋に入れた。そこが獄屋になっていたからである。16 エレミヤは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。」
カルデアの軍勢、すなわちバビロンの軍勢がファラオの軍勢のゆえにエルサレムから引き揚げたときとは、エジプト軍の進撃でエルサレムを包囲していたバビロン軍が一時的に撤退したときのことです。そのとき、エレミヤはエルサレムを出て、ベニヤミンの地に行きました。どうして彼はベニヤミンの地へ行ったのでしょうか。12節には「民の間で割り当ての地を受け取るためであった」とあります。これは既に32章で見たように、彼が従兄弟のハナムエルから買い戻したアナトテにある畑の割り当て地を決めるためだったのでしょう。アナトテの地はベニヤミン族の領地にありましたから。
しかし、彼がベニヤミンの門のところまで来たとき、そこにイルイヤという名の当直の者がいて、彼によって捕らえられてしまいました。それは、エレミヤがバ「ビロンに投降しなさい」と語っていたからです。それで彼はエレミヤがバビロンに逃亡するのではないかと疑われたのです。
エレミヤは、「違う。私はカルデア人のところに落ちのびるのではない。」と否定しましたが、受け入れられず、結局、彼は捕らえられて、首長たちのところに連れて行かれ、投獄されてしまいました。そこは丸天井の地下牢であったとあります。丸天井の地下牢とは、元々貯水槽のために造られたものですが、神のさばきによって雨が降らなかったために泥に覆われた劣悪な環境になっていました。エレミヤは長い間そこに監禁されることになったのです。
この時、エレミヤはどんな気持ちだったでしょう。もうやるせないというか、悔しいというか、苦しいというか、絶望的だったのではないかと思います。十分な審議や取り調べもされずに、誤解されて地下牢に入れられてしまったのですから。
こういうことが私たちにもあります。エレミヤのように投獄されるようなことはないにしても、あなたが職場や友人に自分が教会に行っているということを告げようものなら、あなたは精神的に問題があるのかとか、そんな献金をたくさん取れられるような所に出入りしていて危ないと思われるかもしれません。しかし、主イエスはこう言われました。
「義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。」(マタイ5:10)
神の働きをしていて誤解され、不当に扱われることがあったとしても、義のために迫害され者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。エレミヤは義のために迫害されても、うそや偽りを言って自分を欺くことをしませんでした。それゆえ地下牢に閉じ込められてしまいましたが、そこにはだれも奪うことができない神から与えられる恵みと平安がありました。彼はそれを味わうことができたのです。
こんな証を聞いたことがあります。ある中国人が福音を伝えたことで監獄に入れられました。彼は自分のような足りない者が福音を伝えて投獄されたことは光栄だと喜び、その監獄の中で大声で賛美して、福音を伝えました。すると多くの囚人たちがイエス・キリストに立ち返りました。これを見た看守長は、福音を伝えられないように彼を独房へと移しました。しかし、今度は邪魔されなくてよいと言って、昼も夜も大きな声で賛美しました。結局、看守長は「この人はもうどうにもできない」と彼を釈放しました。釈放後、苦しみを受けたことは大きな感謝だったと言って、以前よりさらに一生懸命に福音を伝える者となりました。
使徒パウロもピリピで投獄されたことがありました。でもそのような苦難を受けることを恐れませんでした。なぜなら、その苦難を通して福音があらゆるところに証しされることを知っていたからです。ピリピ1章13節、14節で彼は、自分がキリストのゆえに投獄されたことによって、ローマの親衛隊全員と、ほかのすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は、主にあって確信が与えられ、恐れることなく、ますます大胆に御言葉を語るようになりました。つまり、そのことが、かえって福音の前進に役立つことになったのです。彼の願いは、どんな場合でも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、彼の身によってキリストがあがめられることだったのです。
「私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。」(ピリピ1:21)
かつて長谷川義信先生が説教の中で、どこを切っても金太郎飴が出てくるように、どこを切ってもイエス・キリストが出てくるような生き方をしなさいと説教で勧められたことがありましたが、まさにそのように生きていたのです。 私たちもそうありたいですね。それは、神はすべてのことを働かせて益としてくださるということを信じて疑わない信仰から生まれます。
どのような困難があろうとも、どんな病に襲われても、どうしてこういうことが起こるのかと思えるような状況に置かれても、確かにキリストは生きておられる、そして今も私と共におられる、私の人生を導いて、私をご自身の栄光の姿へと変えておられるということを聖霊によって受け入れるなら、だれもあなたから喜びと平安を奪うことはできません。誤解されればされるほど、困難な状況に直面すればするほど、悲しみが多ければ多いほど逆に信仰が強められ、さらに主に拠り頼み、主をほめたたえ、主を賛美する者へと変えられていくのです。
Ⅲ.ただ神を恐れて(17-21)
最後に、17~21節をご覧ください。「17 ゼデキヤ王は人を遣わして、彼を召し寄せた。王は自分の家で彼にひそかに尋ねて言った。「【主】から、おことばはあったか。」エレミヤは「ありました」と言った。そして「あなたはバビロンの王の手に渡されます」と言った。18 エレミヤはゼデキヤ王に言った。「あなたや、あなたの家来たちや、この民に対して、私にどんな罪があったというので、私を獄屋に入れたのですか。19 あなたがたに対して『バビロンの王は、あなたがたとこの地を攻めに来ない』と言って預言していた、あなたがたの預言者たちは、どこにいますか。20 今、わが主君、王よ、どうか聞いてください。どうか、私の願いを御前に受け入れ、私を書記ヨナタンの家へ帰らせないでください。私がそこで死ぬことがないようにしてください。」21 ゼデキヤ王は命じて、エレミヤを監視の庭に入れさせ、都からすべてのパンが絶えるまで、パン屋街から毎日パン一つを彼に与えさせた。こうして、エレミヤは監視の庭にとどまっていた。」
丸天井の地下牢に入れられたエレミヤは、長い間そこにいました。少なくとも、数週間から数か月が経過していたことでしょう。するとある日、ゼデキヤは人を遣わしてエレミヤを召し寄せ、自分の家でひそかに彼に尋ねて言いました。「主から、何かおことばがあったか。」この「ひそかに」というのが彼の特徴でした。彼はいつもひそかに行動していました。どうして彼はひそかに尋ねて言ったのでしょうか。それは彼がエルサレムの民や首長たち、そして側近たちを恐れていたからです。もしエレミヤが神からことばがあった、それはバビロンに服しなさいということだったと告げようものなら、彼らから危害を受けるかもしれないと恐れたのです。彼は王であり自由の身でありながら、その心には平安がありませんでした。いつも人を恐れていたからです。しかし、エレミヤはそうではありませんでした。彼は獄屋につながれ自由を奪われていましたが平安がありました。神を恐れていたからです。「人を恐れるとわなにかかる。しかし主に信頼する者は守られる。」 (箴言 29:25)とある通りです。神を恐れるのか、人を恐れるのかです。神に背を向け、神から離れて歩むのか、それとも神とともに歩むのかの違いです。人にどう思われるかを判断基準にするのでなく、御言葉を判断基準にして行く時、神はその心に深い平安を与えてくださるのです。
不安におののきながら質問するゼデキヤに対して、エレミヤはこう答えました。「ありました」。それを聞いたゼデキヤは、「おう、どういう内容か」と興奮したことと思います。しかし、その内容は、これまでエレミヤが語ってきたことと全く変わらないものでした。それは17節にあるように、「あなたはバビロンの王の手に渡されます。」ということでした。そんなことを言ったらゼデキヤ王は喜ばないということがわかっていても、あるいは、たとえ獄屋につながれているような状態でも、それでもゼデキヤにおもねることなく、真実だけを語ったのです。
それに対して、ゼデキヤの預言者たちはどうでしたか。彼らは19節にあるように、「バビロンの王は、あなたとこの地を攻めに来ない。」とゼデキヤが安心するようなことを語っていましたが、バビロンによってエルサレムが包囲されると、彼らは一目散にどこかへ逃げて行ってしまいました。彼らは偽りの言葉を語っていただけでなく、その行動も、忠誠心もすべて偽りだったのです。
箴言にこんなことばがあります。「友はどんなときにも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。」(箴言17:17)
このことで、本当の友は誰だったのかが明らかになりました。本当の友はゼデキヤの預言者たちではなく、エレミヤ本人であったということが明らかにされたのです。エレミヤはエルサレムが滅ぼされた後もそこに続けて、残りのユダヤ人と一緒に暮らすことを選び、そして彼らがエジプトに下ったときも彼らと一緒にいました。ユダヤ人はエレミヤの言葉を嫌い偽預言者の言葉を好みましたが、最後まで一緒にいてくれたのはエレミヤでした。エレミヤこそ、神の真実な愛を持った本当の友だったのです。
ですから、人の言葉には気を付けなければなりません。その時は調子がいいことを言っても、すぐに手のひらを反すかのような行動を取るからです。いつもコロコロ変わるのです。ですから、たとえそれがあなたにとって耳ざわりの良い言葉であっても、心地よい言葉であっても、それが真理であるとは限らないのです。パウロは「教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることなく、むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において、かしらなるキリストに向かって成長するのです。」と言っています。この世には様々な教えの風が吹いていますが、そうした教えに注意しなければなりません。真理を語る人が、真実の愛を持っているのです。
先日、エホバの証人の方が来られて「これ読んでください」と1枚のトラクトを渡してくれました。そのトラクトのタイトルは「世の中これからどうなる?」というものでした。1つ選ぶとしたら・・・ ・良くなっていく ・悪くなっていく ・どちらとも言えない
とても興味のあるタイトルですね。「世の中これからどうなる?」皆さん、世の中これからどうなりますか?そのトラクトには、「あなたには将来と希望がある」(エレミヤ31:17)のみことばを引用して、こんな希望があると書かれてありました。
・楽しくてやりがいのある仕事ができるようになる。
・病気や災害で苦しむことがなくなる。
・家族や友達といつまでも幸せに暮らせる。
この希望が実現するためには、実現させる力、すなわち神が必要であること。もう一つは、実現させたいという気持ちを持つこと。神様は世の中の悪いことを全部なくすと約束している。
皆さん、どう思いますか。本当に聖書にそう書かれてあることでしょうか。そのトラクトに書いてあることは主イエスが再臨した後でもたらされる千年王国においてのことであって、それまでこの世が良くなることはありません。もっと悪くなります。これが聖書が言っていることです。表向きは心地よいことばであっても、それが真理でなかったら滅びに向かうことになってしまいます。真理を語る人が、真実の愛を持っているのです。
このエレミヤの真実な訴えに対して、ゼデキヤは命じて、エレミヤを監視の庭に入れさせ、都からすべてのパンが絶えるまで、パン屋街から毎日パン一つを彼に与えさせました。こうしてエレミヤは監視の庭にとどまることになりました。死の危険を身に覚えた地下牢の獄屋から、監視の庭での監禁生活を続けることになったのです。真実に生きるエレミヤを、神が守ってくださったのです。
あなたはどうでしょうか。こんなことを言えば嫌われてしまうのではないかと、人を恐れてひそかに語っていませんか。それともエレミヤのように、相手が王であろうと誰であろうと、たとえ相手が喜ばないとわかっていても、その人におもねることなく、真実の言葉を語っているでしょうか。「友はどんなときにも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。」
これを実行したのはエレミヤでした。私たちも真実の愛に生きるものでありたいと思います。それは人を恐れ、おもねるような心からではなく、神を恐れ、神と共に歩む真実な心から生まれるのです。
転がしてあった石 マルコの福音書16章1~8節転がしてあった石
聖書個所:マルコの福音書16章1~8節(P104)
タイトル:「転がしてあった石」
復活の主イエス・キリストの御名を心から賛美します。きょうはイースターです。キリストの復活を記念してお祝いする日です。金曜日の午後に十字架の上で息を引き取られ、墓に葬られたイエスは、三日目の朝に、墓を破ってよみがえられました。何と不思議な、何と驚くべきことでしょうか。イエスが葬られていた墓は空っぽだったのです。墓の入り口をふさいでいた石は転がしてありました。先ほどお読みしたマルコ16章4節に「ところが、目を上げてみると、その石が転がしてあるのが見えた。」とあります。口語訳では、「ところが、目をあげて見ると、石はすでにころがしてあった。」と訳しています。石はすでに転がしてあったのです。
私たちの人生にも、私たちの心を塞ぐ石があります。でも私たちがイエスのみもとに行くなら、復活の主イエスがその石をころがしてくださいます。きょうは、この転がしてあった石についてご一緒に思い巡らしたいと思います。
Ⅰ.だれが石を転がしてくれるか(1-3)
まず1~3節までをご覧ください。「1 さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメは、イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。2 そして、週の初めの日の早朝、日が昇ったころ、墓に行った。3 彼女たちは、「だれが墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか」と話し合っていた。」
十字架で死なれたイエスのからだは、アリマタヤのヨセフによってまだだれも葬られたことのない新しい墓に埋葬されました。このアリマタヤのヨセフはイエスの弟子でしたが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していました。しかし彼は、勇気を出してピラトにイエスのからだの下げ渡しを願うと、ピラトはそれを許可したので、イエスが十字架につけられた場所のすぐ近くにある墓に葬ったのです。というのは、すでに夕方になっていて、もうすぐ安息日(土曜日)が始まろうとしていたからです。安息日が始まったら何でできなくなってしまうので、その前に彼は急いでイエスのからだを十字架から取り降ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣にしたがって、イエスのからだをその墓に埋葬したのです。
その安息日が終わると、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメは、イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買いました。油を塗るとは、香料を塗るということです。
これらの女性たちは、ずっとイエスにつき従って来た人たちでした。彼女たちは最後の最後までイエスに愛と敬意を表したかったのです。それはイエスが自分に何をしてくれたのかを知っていたからです。特にマグダラのマリアは七つの悪霊を追い出してもらいました。一つじゃないですよ。七つです。七つの悪霊です。一つの悪霊でも大変なのに彼女は七つの悪霊に取り憑かれていました。それは、彼女が完全に悪霊に支配されていたということです。身も心もズタズタでした。しかし彼女はそのような状態から解放されたのです。どれほど嬉しかったことでしょう。感謝してもしきれないほどだったと思います。イエスがいなかったら今の自分はない。イエスはいのちの恩人以上の方。最も愛すべき方。その方が苦しんでいるならほっておけません。何もできないけれども、せめてイエスの傍らにいたい。どんな目に遭おうと、たとえ殺されようとも、イエスのみそば近くにいたかったのです。イエスは自分にとってすべてのすべてだから。そういう女性たちが複数いたのです。
彼女たちは、安息日が終わったので、イエスに油を塗ろうと思い、香料を買い、週の初めの日の早朝、日が昇ったころ、墓に向かって行きました。新共同訳では、「日が出るとすぐ墓に行った。」と訳しています。そうです、彼女たちはもう待ちきれませんでした。日が昇るとすぐに墓に行ったのです。
しかし、墓に向かっている途中で、彼女たちは一つの問題があることに気付きました。何でしょうか?それは、墓の入り口が大きな石で塞がれていることです。だれがその石を転がしてくれるでしょうか。この石は重さ2~2.5tもある重い石で、女性たちが何人いても女性の力では動かせるようなものではありませんでした。男でもよほどの人数がいなければ動かせないほどのものです。
しかも、その石はただの石ではありませんでした。並行箇所のマタイ27章66節を見ると、その石には封印がされていたとありました。これはローマ帝国の封印で、これを破る者は逆さ十字架刑にされることになっていました。ですから、そこには番兵もつけられていました。屈強なローマ兵たちが、24時間体制で監視していたのです。その石を動かさない限り、中に入ってイエスのからだに香油を塗ることはできません。とても無理です。それでも女性たちは墓に向かって行きました。無理だ、不可能だと思っても、です。
3節には、彼女たちは「話し合っていた」とありますが、彼女たちは、どこで何を話し合っていたのでしょうか。「だれが墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか」と、墓に向かっている最中で話し合っていました。
ここが男性とは違うところです。一般の男性ならどうするでしょうか。まず行く前に会議を開くんじゃないです。「行っても無駄だ。墓の入り口にある石をどやって動かすのか。そこにはローマ兵たちがいるじゃないか。どう考えても無理に決まっている。その前に香料を買ってもただのお金の無駄遣いだ」と。
これが一般の男性が考えることです。でも女性は違います。女性は一般的に心に感じるまま行動します。そうしたいと思ったらあまり考えずにすぐにそれを行動に移します。こんなことを言ったら女性を差別しているのではないかと叱られるかもしれませんが、別に女性を差別しているのではありません。それが女性のすばらしいところだと言っているのです。とにかく安息日が明けたらイエスのもとに行きたい。1秒でも早く会いたいと思う。その愛が彼女たちを突き動かしたのです。その前に立ちはだかった大きな石も、彼女たちにとっては問題ではありませんでした。愛がなければその大きな石を前にして何もできなかったでしょう。「あの石をどうしよう」で終わっていたはずです。でも愛は不可能を可能にします。「愛には、計算が成り立たない」と言った人がいます。彼女たちの行動は、まさに計算が成り立ちません。しかし、それが愛なのです。考えてみれば、イエス様の生涯もそうだったのではないでしょうか。計算では成り立ちません。この世の目から見たら愚かなことのように見えます。その極めつけが十字架です。十字架で死なれることでした。主はご自身に敵対する人を救うために十字架にかかって死んでくださいました。そして、その上でご自分を十字架につけた人々のためにとりなしの祈りをささげたのです。このような愛は、この世の常識では考えられません。人間の計算をはるかに超えています。しかし、そうでなければ見いだせない大切なことがあるのです。そのことに気付かないと、大切なものを失ってしまうことがあるのです。
注目すべきことは、彼女たちがここで「だれが」と言っていることです。「だれが墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。」と。この「だれが」が重要です。彼女たちは自分たちにはできないことが最初から分かっていたので、だれか他の人に頼らなければなりませんでした。「だれが墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。」でも男性はそう考えません。男性はこう考えます。「どうやって」。どうやってあの石を転がすことができるかと。いつも頭の中で考えてばかりいて行動に移せないのです。でも女性は違います。彼女たちは「なぜ」とか「どうやって」ではなく「だれが」と言いました。なぜ男の弟子たちは一緒に来ないのかとか、どうやって墓の入り口から石を転がしたらいいかではなく、だれが転がしてくれるかと言ったのです。
皆さん、「だれが墓の入り口の石を転がしてくれるのでしょうか。」そうです、イエス・キリストです。イエスが死からよみがえって墓から石を転がしてくださいます。ですから、この女性たちの「だれが」という問いには、彼女たちの信仰が表れていたということです。
これは私たちにも問われていることです。私たちは「だれが」の前に「どうやって」と問うてしまいます。「なぜ」こういうふうになっているのか、「いつ」「どこへ」行ったらいいのかと、その状況とか、方法とかを考えてしまうあまり、何もできなくなってしまうのです。でも彼女たちは違いました。もう動いています。動いている最中で「だれが墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか」と話し合っていました。彼女たちは自分たちにできないことは考えませんでした。だれかがしてくれると信じていたのです。彼女たちは、復活の信仰を持っていたとも言えるでしょう。それは私たちにも求められていることです。「どうやって」ではなく、復活の主があなたの心を塞いでいる石を転がしてくださると信じて、イエスのもとに行かなければならないのです。
Ⅱ.石はすで転がしてあった(4)
次に、4節をご覧ください。ご一緒に読みましょう。「ところが、目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。」
彼女たちが墓に行ってみると、墓はどうなっていましたか。あの石が転がしてありました。新改訳第3版、口語訳、新共同訳、創造主訳のいずれの訳では「すでにころがしてあった。」と訳しています。その石はすでに転がしてありました。イエスに近づくことを妨げていたあの大きな石が、すでに取り除かれていたのです。彼女たちのイエスを愛する愛に、神様が応えてくださったのです。
それはあなたにも言えることです。あなたがイエスに会いに行こうとする時、そこに大きな石のような問題が立ちはだかっていることがあります。でもその時、「どうやって」とか「いつ」とか「なぜ」と問わないで、「だれが」と問うなら、イエスがあなたの問題をすでに解決してくださいます。女性たちがイエスの墓に到着したら、石はすでに転がしてありました。もしあなたがイエスを信じ、イエスを愛するなら、どんな問題でもイエスが解決してくださるということを知ってください。この女性たちのように。彼女たちはイエスの亡骸に向かう道中で「だれがこの問題を解決してくれるか」と問うていましたが、そのだれがとは、もちろん、イエスです。イエスはすでにあなたの悩みを解決しておられます。もしあなたがキリストのもとに行くなら、あなたの問題はもうすでに解決されています。あの大きな石は転がしてあるのです。彼女たちが墓に向かったのは、まだ暗いうちでした。人生の暗いうちにはまだ大きな石がたちはだかっています。でもあなたがキリストに向かって歩き始めるなら、どんなに人生が暗かろうと、どんなに大きな問題が立ちはだかろうと、どんなにそれが不確かであろうと、キリストがそれを取り除いてくださるのです。あなたに求められているのは、イエスがこの石を転がしてくださると信じて、イエスのもとに歩き出すことです。
榎本保郎先生が書かれた「ちいろば」という本の中に、こんな話があります。
榎本先生が開拓した教会に、T君という、1人の高校生が来ていました。とてもやんちゃな子でしたが、熱心に求道するようになり、いつしか高校生会のリーダーになりました。
そのT君が高校3年生の時、献身者キャンプに参加しました。献身者キャンプとは、将来、牧師になることを決心するためのキャンプです。榎本先生も、講師の一人として、参加しました。そのキャンプの最後の集会で、「献身の志を固めた人は、前に出て、決心カードに署名しなさい」、という招きがなされました。
招きに応えて、泣きじゃくりながら、立ち上がる者。こぶしで涙を拭いながら、前に進み出る者。若者たちが、次々に立ち上がって、震える手で、署名しました。しかし、T君は、なかなか前に出て行きません。頭を垂れて、じっと祈っていました。しかし、招きの時が終わろうとした時、遂に、T君は、立ち上がって前に進み、決心カードに、名前を書き込みました。
席に戻ってきたT君は、真っ青になって、ぶるぶる震えていました。決心したことで、心が高揚したこともあったと思います。しかし、T君には、もっと深刻な、問題があったのです。
T君は、とても勉強のできる生徒でした。ですから、両親は、大きな期待を、彼に懸けていました。両親は、彼が、京都大学の工学部に入ることを、ひたすら願っていたのです。それが、両親の、生き甲斐とも、言えるほどでした。それなのに、もし、T君が牧師になる決心をした、と聞いたなら、両親は、どんな思いになるだろう。がっかりするだろうか。怒るだろうか。その両親の期待の大きさを身に沁みて知っていただけに、T君は、両親に、どのように打ち明けたらよいか、途方に暮れていたのです。そして、両親の落胆と、怒りを、想像しただけで、いたたまれない気持ちになっていたのです。
T君は、真っ青になって、「先生、祈ってください」、と榎本先生に頼みました。先生にも、その気持ちがよく分かりました。そこで榎本先生とT君は、ひたすら祈りました。祈るより他に、すべはなかったのです。その時、榎本先生の心に浮かんだのが、この4節のみことばでした。「石はすでに転がしてあった」。
榎本先生は、「T君、神様は、必ず、君の決心が、かなえられるように、備えてくださる。『石は、すでに転がしてあった』、という御言葉を信じよう」、と力づけました。
それを聞いて、T君は帰っていきました。しかし、T君から、両親との話し合いの結果が、なかなか報告されてきません。榎本先生は、どうなったか、心配でたまらず、T君の家の前を、行ったり来たりしていました。
帰ってから、三日たった夕方、げっそりやつれたT君が、教会にやってきました。そして「先生、石は、のけられていませんでした」、と言ったのです。父親は激しく怒り、母親は食事も取らずに、ただ泣き続けている、という報告でした。
榎本先生は、暗い気持ちになって、「どないする?よわったなぁ」と、呟きました。その時、「先生、『石はすでに転がしてあった』というあの御言葉は、どうなっとるんですか」。というT君の鋭い言葉が迫ってきました。先生は、自分の不信仰に気付かされ、「いや、あの御言葉は、君にも必ず成就するよ」と、T君と自分自身に言い聞かせました。
それから半月ほど経った頃です。T君の両親が、教会を訪ねてきました。「息子をたぶらかした悪者」、と罵倒されるものと思って、戦々恐々として迎えた榎本先生は、びっくりしました。というのは、T君の両親がこう言ったからです。
「先生、息子を、よろしくお願いします」。
頭を下げたお父さんは、両肩を震わせながら、じっと涙をこらえていました。お母さんは、手をついたまま、泣きじゃくっていました。両親は、T君の献身を、許してくれたのです。
「石は、すでに転がしてあった」のです。この御言葉は、T君の上に、見事に成就しました。その後、T君は、牧師となって、よい働きをしているという内容です。
皆さん、私たちの人生にも大きな石が立ちはだかることがあります。しかし、あなたがイエスを愛し、イエスに向かって歩むなら、イエスがその石を転がしてくださいます。ですから、どこまでも最善に導いてくださる主に信頼して、祈り続けましょう。そうすれば、あなたも必ず「石は、すでに転がしてあった」という、神様の御業を見るようになるからです。
Ⅲ.弟子たちとペテロに告げなさい(5-8)
最後に、5~8節をご覧ください。「5 墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が、右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。6 青年は言った。「驚くことはありません。あなたがたは、十字架につけられたナザレ人イエスを捜しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。7 さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。『イエスは、あなたがたより先にガリラヤへ行かれます。前に言われたとおり、そこでお会いできます』と。」8 彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そしてだれにも何も言わなかった。恐ろしかったからである。
〔彼女たちは、命じられたすべてのことを、ペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後、イエスご自身が彼らを通して、きよく朽ちることのない永遠の救いの宣言を、日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。〕」
女性たちが墓の中に入ってみると、そこにまっ白な衣をまとった青年が、右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚きました。青年は彼女たちにこう言いました。6節です。「驚くことはありません。あなたがたは、十字架につけられたナザレ人イエスを捜しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。」
ここでは「驚いた」ということばが強調されています。イエスのからだが納められていた墓からあの石が転がされていただけでなく、その墓の中は空っぽだったからです。なぜ墓は空っぽだったのでしょうか?イエスがよみがえられたからです。イエスは死んで三日目によみがえられ、その墓を塞いでいた大きな石をころがしてくださったのです。それを見た女性たちはどんなに驚いたことでしょう。そして、私たちも同じ体験をすることになります。私たちの心を塞いでいた大きな石が転がされるという体験です。どんなに悩みがあろうと、どんなに疑問があろうと、どんなに問題があろうと、イエスはあなたの心に立ちはだかる石を転がしてくださいます。なぜなら、イエスはみがえられたからです。
ところで、この青年は彼女たちにもう一つのことを言いました。それは7節にあることです。「さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。『イエスは、あなたがたより先にガリラヤへ行かれます。前に言われたとおり、そこでお会いできます』と。」」
ここで青年は、イエスが弟子たちより先にガリラヤに行くので、そこでお会いすることができると言いましたが、ここでは弟子たちだけでなく、弟子たちとペテロにと言っています。あえて使い分けているのです。弟子たちだけでなく、ペテロに対して個人的に伝えてほしいと。なぜ「弟子たちに」ではだめだったのでしょうか。なぜ個人的にペテロに告げる必要があったのでしょうか。
それはペテロが弟子たちの筆頭であったからではありません。それは、ペテロが一番イエスに会いづらい人物だったからです。なぜなら、彼は公の場で3度もイエスを否定したからです。彼は「他の弟子たちがすべてあなたを見捨てても、私だけは火の中水の中、死までご一緒します。口が裂けてもあなたを知らないとは絶対に言いません。」と言い張ったのに、イエスを知らないと否定しました。今さら、どの面下げて主に会えるでしょう。弟子の筆頭だった彼が一番してはいけないことをしたのです。イエスの目の前で。
でもペテロは先にイエス様にこういうふうにも言われていました。ルカ22章31~32節のことばです。
「シモン、シモン。見なさい。サタンがあなたがたを麦のようにふるいにかけることを願って、聞き届けられました。しかし、わたしはあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」
イエスはすべてのことがわかっていました。十分わかった上で、あなたの信仰がなくならないように祈った」と言われたのです。そして「ですから、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。」と言われました。これは「もし立ち直ったら」ということではありません。イエスは彼が立ち直ることもちゃんとご存知の上で、それを前提にして、あなたが立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさいと言ったのです。失敗した人にやり直しをさせて、兄弟たちを力づけてやるという新しい務めも与えると、イエスはあらかじめ約束しておられたのです。ですから、イエスはその約束通りにまずペテロの前に現れ、その約束を果たされるのです。まずペテロを立ち直らせる。これが復活された主がなさる最初のことだったのです。イエスのことを3度も否定した弟子の筆頭、その立場なり、その資格を失っている者に対して、まず回復をもたらしたのです。つまり、イエスは一番傷ついている者、一番痛い思いをしている者、一番恥ずかしい思いをしている者のところへ行って、和解をもたらしてくださるということです。ペテロはとてもイエスの復活の証人として相応しいとは思えません。しかし、そのようなペテロを主はあわれんでくださり、復活の姿を現わしてくださったのです。
それは私たちも同じです。このイエスの愛は、同じように私たち一人ひとりに注がれています。神様に背いてばかり、神様になかなか従えないこんな私をイエスは愛し恵みを注いでいてくださる。私たちも復活の主によって支えられ、復活の主の弟子とされているのです。弱いペテロをどこまでも愛され「そうそう、あのペテロにも伝えなさい」と仰せられた主は今、私たち一人ひとりにも、語り掛けてくださっているのです。「そう、そう、あのおっちょこちょいの富男さんにも伝えてあげなさい。何度言ってもわからない。同じ失敗を繰り返しているあの人にも」と。救われるに本当に相応しくないような者であるにもかかわらず、主は一方的な恵みをもって救ってくださいました。あなたがペテロのように主を否定するような者であっても、パウロのように教会を迫害するような者であっても、復活の主はあなたをどこまでも愛しておられるのです。
最後に8節をご覧ください。「彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そしてだれにも何も言わなかった。恐ろしかったからである。〔彼女たちは、命じられたすべてのことを、ペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後、イエスご自身が彼らを通して、きよく朽ちることのない永遠の救いの宣言を、日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。〕」
彼女たちは墓を出ると、そこから逃げ去り、そのことを誰にも言わなかったとありますが、実際には、ペテロにも、他の弟子たちにも伝えています。これはペテロと弟子たち以外には、だれにも伝えなかったという意味です。つまり、彼女たちは、復活の主の最初の証人となったということです。最初の証人となったのはイエスの12人の弟子たちではなく、この女性たちだったのです。これはすごいことです。というのは、当時、イエス様の時代は、女性が証人になることは考えられないことだったからです。しかし、そんな女性たちがイエスの復活の最初の目撃者となりました。男たちではありません。女たちです。
復活のメッセージを伝えることは、実に栄誉ある務めです。その栄誉に与ったのはこの女性たちだったのです。なぜでしょう?男たちは「どうやって」と考えると何も出来なかったのに対して、彼女たちはどんなに大きな石が目の前に立ちはだかっていても、どんなに屈強なローマ兵が監視していようとも、たとえ捉えられて死ぬことがあっても構わない、とにかくイエスに会いたい。愛するイエスに会いたい。その一心で動いていたからです。
それに対してなされた大いなる神様の御業を、私たちは今ここで見ているのです。これは男か女かの違いを言っているのではありません。これは、信仰か不信仰かの違いです。イエスを愛しているか、いないのかの違いです。彼女たちには信仰があり、イエスに対する愛がありました。そして、イエスの復活によって希望まで与えられました。この女性たちは、私たち信仰者の模範です。私たちもこの女性たちのようにイエス様を愛するゆえに、「どうやって」ではなく「だれが」石を転がしてくださるのかと問いながら、復活の主がそれをなしてくださると信じて、心から主を愛し、主につき従う者でありたいと思います。イエスはよみがえられました。死からよみがえられた主は、あなたの前に立ちはだかるいかなる石も必ず転がしてくださるのです。
三本の十字架 ルカの福音書23章32~43節 三本の十字架
聖書箇所:ルカの福音書23章32~43節
タイトル: 「三本の十字架」
今日から受難週が始まります。それはイエス様が十字架の死という受難に向かって歩まれた最期の一週間です。ちょうど今週の金曜日が十字架につけられたその日に当たり、そこから数えて三日後の、来週の日曜日の朝に、イエス様は復活されました。ですから、来週はイエス様が復活されたイースターをお祝いしたいと思いますが、今日はその前にイエス様が十字架で苦しみを受けられた出来事からメッセージを取り次ぎたいと思います。タイトルは「三本の十字架」です。33節には、イエス様が十字架につけられた時、イエス様の右と左にそれぞれ二人の犯罪人も十字架につけられたとあります。ですから、そこには三本の十字架が立てられていたのです。
Ⅰ.父よ、彼らをお赦しください(32-38)
まず、最初の十字架、イエスの十字架から見ていきましょう。32~38節をご覧ください。「32 ほかにも二人の犯罪人が、イエスとともに死刑にされるために引かれて行った。33 「どくろ」と呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。34 そのとき、イエスはこう言われた。「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。」彼らはイエスの衣を分けるために、くじを引いた。35 民衆は立って眺めていた。議員たちもあざ笑って言った。「あれは他人を救った。もし神のキリストで、選ばれた者なら、自分を救ったらよい。」36 兵士たちも近くに来て、酸いぶどう酒を差し出し、37 「おまえがユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」と言ってイエスを嘲った。38 「これはユダヤ人の王」と書いた札も、イエスの頭の上に掲げてあった。」
イエス・キリスト以外にも二人の犯罪人が、イエスとともに死刑にされるために連れて行かれました。この二人の犯罪人は、並行箇所のマタイの福音書27章38節を見ると「強盗」と記されてあります。つまり、彼らは十字架刑に値するような重罪を犯したわけです。
彼らが連れて行かれたのは「どくろ」と呼ばれていた場所でした。ギリシャ語では「クラニオン」と言います。ヘブル語では「ゴルゴタ」、ラテン語で「カルバリー」です。英語の「カルバリー」はラテン語から来ています。それは響きはいいですが、意味は「どくろ」です。私が最初に開拓した教会は、「北信カルバリー教会」と名付けました。「北信どくろ教会」です。なぜそういう名前にしたのかというと、その地域が「北信」という地域であったということと、アメリカの教会が「ガーデナ・カルバリーチャーチ」という名前だったからです。それで「北信」に「カルバリー」を付けて「北信カルバリー教会」としたのです。でも実際は「どくろ教会」です。なぜその場所が「どくろ」と呼ばれていたのか、そこは死刑場で骨が散らばっていたからだとか、この丘の形がどくろの形をしていたからという説があります。その「どくろ」と呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけました。イエスだけではありません。ほかに二人の犯罪人がいて、彼らも十字架につけられました。一人はイエスの右に、一人はイエスの左に、です。ですから、そこには三本の十字架が立てられていたのです。
34節をご覧ください。「そのとき、イエスはこう言われた。「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。」彼らはイエスの衣を分けるために、くじを引いた。」
これはイエスが十字架上で発せられたことばです。イエスは十字架の上で七つのことばを発せられましたが、これはその最初のことば、第一のことばです。「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。」十字架の上でイエスは開口一番とりなしの祈りをされました。これはイエスが自らの教えを実践されたということです。ルカの福音書6章27~28節には、「しかし、これを聞いているあなたがたに、わたしは言います。あなたがたの敵を愛しなさい。あなたがたを憎む者たちに善を行いなさい。あなたがたを呪う者たちを祝福しなさい。あなたがたを侮辱する者たちのために祈りなさい。」とあります。イエスはまさにこれをご自分に適用されたのです。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行うように。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。なかなかできないことです。でもイエスはこれを自ら実践されました。その究極がこの十字架上でのとりなしの祈りだったのです。この時イエスはボコボコにされていました。血まみれの状態で、それがイエスだと判別することができないほどだったのです。それでもイエスはこのように祈られました。「父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分からないのです。」
この「彼ら」とは誰のことでしょうか。直接的にはイエスを十字架にかけた死刑執行人たち、ローマの兵士たちのことでしょう。そして直接的には手をかけなくても、彼らに死刑をやらせたポンテオ・ピラトもそうでしょうし、イエスを殺そうと企んでいたユダヤ人の当局者たちもそうです。さらには、そうした宗教家たちに先導されて「十字架につけろ、十字架につけろ」と叫んだ群衆たちもそうです。強いて言うなら、私たちもそうです。私たちもこの「彼ら」に含まれるのです。なぜなら、私たちも自分が何をしているのかわかっていないからです。自分が罪を犯しているかどうかさえもわかっていない人たち、罪を罪とも感じない人たちのためにイエスはこのようにとりなしの祈りをされたのです。
このときイエスはどういう状態でしたか。もうひん死の状態でした。その声は虫の息のようで、ことばを発するのが奇跡に近いような状態でした。そういう状態でイエスは自分のことではなくそんな「彼ら」のために祈られたのです。皆さん、自分の手に釘を打ち付けたことがありますか。そういう経験はないかと思いますが、想像してみてください。想像しただけでゾッとします。かなりの痛みが体全体に走るでしょう。すべての神経がその一点に集中します。もう他の人のことなど全く考えられないはずです。余裕で何かことばを発するなんてできなくなります。しかし、イエスは自分のことなど全く無視するかのように、「父よ、彼らをお赦しください。」と祈られました。それはイエスがそのためにこの世に来られたということをだれよりもよく認識していたからです。ですから、イエスは激しい痛みと苦しみの中にあってもそのことを忘れず、最後まで忠実に神のみこころを果たそうとされたのです。十字架の上でもなおも人を救おうと願っておられたからです。
このことばは、古今東西多くの人たちの心をとらえてきました。まさに心を奪われてイエスによって救われた人たちが後を絶ちません。特に紹介したいのは、淵田美津雄(ふちだみつお)という人です。この人は真珠湾攻撃の総隊長、海軍大佐だった人です。のちにクリスチャンになってキリスト教の伝道者になりますが、彼がクリスチャンになったきっかけがこの聖句でした。「父よ、彼らを赦したまえ。その成すところ知らざればなり。」このことばが彼の心を捉えて、彼は救われました。そして世界中を伝道して回る伝道者になったのです。アメリカと日本の橋渡しとなって、赦しのメッセージを伝えて行くことになりました。このイエスのことばによって、その後も多くの人たちが救われていくことになります。
私たちはもう一度自分の原点を振り返りながら、私たちはどこから救われて来たのかを考えなければなりません。私たちはどこから救われて来たのでしょうか。ここからです。このイエスのとりなしの祈りから救われて来ました。これが私たちの救いの原点です。私たちもイエス・キリストを十字架に磔にした「彼ら」、極悪人とちっとも変わりません。それなのにイエスはそんな私たちのために祈られたのです。本来ならこの私が十字架に付けられて死んでいなければならなかったのに、そんな私たちのためにイエスがとりなしてくださったことによって救われたのです。ここから私たちの救いの物語が始まっているのです。イエスがこのとりなしの祈りをささげられなかったら、私たちは救われませんでした。イエスの祈りだからこそ、父なる神は聞いてくださったのです。
35節をご覧ください。民衆は立って眺めていました。議員たちも、あざ笑って言いました。「あれは他人を救った。もし神のキリストで、選ばれた者なら、自分を救ったらよい。」この議員たちとはユダヤ教の宗教指導者たちのことです。彼らも十字架につけられたイエスを見てあざ笑って「あれは他人を救った。もし神のキリストで、選ばれた者なら、自分を救ったらよい。」と言ってしまいました。言ってしまったというのは、思わず言ってしまったということです。これは「ウップス!」です。思わず本音が出ちゃったということです。「あれは他人を救った」それは真実のことばです。他人を救ったなんて本当は言いたくなかったのです。他人を救ったようだったとか、救ったと自慢したとか、そんなふうに言いたかったのに、思わず本当のことを言ってしまいました。「あれは他人を救った。」そうです、イエスは他人を救ったのです。イエスの敵であった彼らでさえも、それを認めていたということです。彼らは知っていました。イエスが神の力で他人を救ったということを。だったら自分を救ってみろと。
皆さん、イエスは自分を救うことができなかったのでしょうか。いいえ、彼は自分を救うことなど何でもないことでした。たとえば、イエスが十字架につけられるためにローマの兵士約600人がイエスを捕らえに来たとき、イエスが彼らに「だれを捜しているのか」と言うと、彼らは「ナザレ人イエスを」と答えましたが、そのときイエスが「わたしがそれだ」と言うと、彼らは後ずさりして、地に倒れてしまいました。「わたしがそれだ」と言っただけで、600人の兵士が一度に倒れてしまったのです。また、イエスが風に向かって「嵐よ、静まれ」と言うと、すぐに凪になりました。風や波すらイエスの言うことに従ったのです。自然の猛威ですらイエスの権威の前に服するのですから、ローマ兵が何人束になってかかって来ても、イエスにかなうわけがありません。イエスは自分を救うことなんてお茶の子さいさいだったのです。十字架の上から下りることなんて何でもないことでした。でもそうされませんでした。なぜ?そんなことをしたら私たちを救うことができなくなってしまうからです。イエスはそのことを十分知っておられたので、そのような彼らのことばに乗ることをしませんでした。誘惑はあったでしょう。こんなひどいことを言われるくらいならさっさとここから下りて天の父のところに帰って行こういうこともできたはずです。でもそうされませんでした。あえて十字架の上にとどまられたのです。それは私たちを愛するゆえです。釘がイエスを十字架にとどめたのではありません。私たちに対する愛が、イエスを十字架にとどめたのです。そのことをもう一度覚えていただきたいと思います。
36~38節をご覧ください。「36 兵士たちも近くに来て、酸いぶどう酒を差し出し、37 「おまえがユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」と言ってイエスを嘲った。38 「これはユダヤ人の王」と書いた札も、イエスの頭の上に掲げてあった。
ユダヤ教の宗教指導者たちだけでなく、ローマの兵士たちもイエスをあざけりました。彼らは十字架に磔にされたイエスの近くに来て、「酸いぶどう酒」を差し出しました。この酸いぶどう酒というのは、発酵が進んだぶどう酒に水を混ぜ合わせたものです。これは酔うためではありません。渇きを潤すためのものです。十字架刑があまりにも過酷な刑だったので、あわれみがかけられ、麻酔薬に相当する没薬を混ぜたぶどう酒が差し出されたのです。でもイエスはそれを飲もうとされませんでした。はっきりした意識を持ってその痛みの一つ一つを感じながら、私たちの罪の贖いを成し遂げられたのです。これが私たちに対するイエスの愛でした。つまり、イエスは十字架でご自身の愛を明らかにしてくださったのです。カルバリ山のイエスの十字架は、その神の愛の表れだったのです。それほどまでにあなたは愛されているということです。
イエスはかつて、こう仰せられました。「人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません。」(ヨハネ15:13)。人がその友のためにいのちを捨てるということよりも大きな愛はありません。それは最も大きな愛です。誰かを本気で愛そうと思うなら、その人のために、自分のいのちを捨てて、身代わりとなる、それ以上にその愛を最大限に表せる方法はなありません。なぜなら、人が犠牲にすることのできる最大のものは「自分のいのち」に他ならないからです。そしてあのゴルゴタの十字架、カルバリの十字架で、イエスはまさにその「ご自分のいのち」を私たちのための身代わりとなって捨てて下さったのです。 しかも「神の御子のいのち」は、「私たちのいのち」と違います。「罪の汚れ」というのが一点たりともありませんでした。私たちは多かれ少なかれ罪を抱えています。だから、本当は私たちだってあの十字架の上で罰せられても仕方のない者なのです。しかし神の御子は違います。イエスはそのような罪を何一つ犯しませんでした。十字架刑には全く値しないお方だったのです。重罪どころか軽犯罪すら犯しませんでした。ローマの法律ばかりか、ユダヤの律法にも違反していませんでした。イエスは全く罪のない方だったのです。そのイエスが十字架に付けられたのです。なぜでしょうか?それは私たちを救うためです。そのためにイエスは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったのです。これこそ「愛」というものなのではないでしょうか。これより大きな「愛」はありません。だから、神様は、私たちのことを間違いなく愛して下さっています。だって私たちは、その「しるし」をこの十字架に、しっかりと見せていただいているのですから。
朝鮮戦争の時、二人の若いアメリカ人兵士が、とある塹壕に隠れていました。二人は大の仲良しで、いつも一緒に行動していたそうですが、ある日、二人が隠れていた塹壕に手榴弾が投げ込まれました。すると、それを見た一人が、もう一人の方にウィンクするや、その手榴弾の上に自分の体を投げ出して覆い被さったというのです。当然、その人は亡くなりましたが、その尊い犠牲によってもう一人の方は、無事にいのちが守られました。
その後、生き残った兵士はアメリカに帰ってから、自分を助けてくれた友だちのお母さんに会いに行きました。そしてお母さんに尋ねました。「彼は、手紙の中でボクのことを書いていましたか?」すると「ええ」とお母さんが答えてくれたので、さらに彼は、「手紙の中で、ボクのことを愛していると書いていましたか?」と訊ねました。すると、そのお母さんは、突然持っていたカップを床に投げつけて、こう言いました。「あんたは、一人の男があんたのためにいのちを捨てたのに、『彼があんたを愛していたか』って聞くの?」と。
私たちも神様に対して、これと同じようなことをしてはいないでしょうか。「あなたは、神の御子なるお方があの十字架で、あなたのためにいのちを捨てて下さったのに、神さまの愛を疑うのか」と言われるようなことをしていないでしょうか。
Ⅱ.わたしを思い出してください(39-42)
次に、イエスの右と左に立てられた二人の犯罪人の十字架を見ていきましょう。39~42節をご覧ください。「39 十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスをののしり、「おまえはキリストではないか。自分とおれたちを救え」と言った。40 すると、もう一人が彼をたしなめて言った。「おまえは神を恐れないのか。おまえも同じ刑罰を受けているではないか。41 おれたちは、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は、悪いことを何もしていない。」42 そして言った。「イエス様。あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。」」
並行箇所のマタイの福音書27章44節を見ると、最初イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちは、二人ともイエスをののしっていました。しかし、ここでは一人の犯罪人がイエスをののしっていて、もう一人の犯罪人はイエスを信じ、イエスをののしっていたもう一人の犯罪人をたしなめています。すなわち、ある段階から一人は変えらたということです。イエスの右と左、全く同じ距離に磔けられた二人の犯罪者。二人とも強盗であり、二人とも罪深い者でした。でも何かが変わったのです。犯罪者の一人は、イエスをののしり、「おまえはキリストではないか。自分とおれたちを救え。」と言い、もう一人はイエスを信じて、「おれたちは、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は、悪いことを何もしていない。」と言い、イエスに「あなたが御国に入れられるときには、私を思い出してください。」と言いました。いったいこの違いはどこから生じたのでしょうか。
これまでも35節と37節には、「自分を救ってみろ」という言葉が使われていました。35節ではユダヤ教の宗教指導者たちとそれに先導された一般民衆たちから、37節ではローマの兵士たちから、そのようにののしられました。そして、この39節では一人の犯罪人からののしられています。「自分とおれたちを救え」と。彼らに共通していることは何かというと、今置かれている目の前の苦しみから解放してみろ、救ってみろということです。日本語の聖書はきれいなことばで訳されていますが、原語では、ひどいニュアンスのことばが使われています。「おめえはキリストなんだろ。だったら、てめえ自身と俺たちのことを救ってみろ!」そんな感じです。いわばヤケクソです。このヤケクソは、私たちもよく経験することではないでしょうか。自分の力ではどうにもならない現実に押し潰されるとき、人は皆こんなふうにヤケクソになりやすいのです。それはクリスチャンだって同じです。それは「神様の愛を疑う程の失望」から湧き上がって来るものです。
しかし、もう一人の犯罪人は違いました。もう一人の犯罪人は、彼をたしなめてこう言いました。「おまえは神を恐れないのか。おまえも同じ刑罰を受けているではないか。おれたちは、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は、悪いことを何もしていない。」そして言った。「イエス様。あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。彼は「ここから下せ」とか、「おれたちを救え」と言ったのではありません。彼は「イエス様。あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。」と言いました。つまり、「ここから引き上げてください」と言ったのです。もっと高い次元にいざなってください。もっとあなたのみぞは近くに置いてください。もっとあなたを知りたいのです、そう言ったのです。この苦しみからただ解放してほしいというのではなく、この苦しみの中にあってもあなたをもっと知りたい。もっとあなたに近づきたいと言ったのです。詩篇119篇71節にこうあります。「苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。それにより、私はあなたのおきてを学びました。」
すばらしいですね。この苦しみを通してイエスの苦しみに少しでも預かることができるのであればそれこそ本望だ。それは本当にありがたい。苦しいけれどもありがたい。これによってイエスの似姿に変えられるならば、私は喜んでこの苦境を耐えていきたい。そう言ったのです。あなたはどうでしょうか。あなたの祈りはそうなっているでしょうか。
それとも、もう一人の犯罪人のように「自分とおれたちを救え。」の一点張りでしょうか。「とにかくここから早く下してくれ。解放してくれ。」と。病気になったらすぐに癒してください。困ったことがあったらすぐに助けてください。あれがないからこれをください。これがなければあれをください。ああしてください。こうしてください。そういう祈りになってはいないでしょうか。そういう祈りが決して悪いと言っているのではありません。しかし、それはこの一人の犯罪人とちっとも変わりません。ただ目の前の苦しみから解放してほしいというだけです。しかし、仮にイエスがこの祈りに応えたとしても、結局、この強盗はどうなったでしょうか。結局、自分の罪の中に死んでいくことになります。その時は一時の救いを経験するかもしれませんが、究極的には地獄に堕ちて行くことになるのです。確かに目の前の苦しみから解放されたいでしょう。できるだけ早くそこから救ってほしいと思うのは当然のことです。でも主が求めておられることは、自分とおれたちを救えということではなく、「イエス様。あなたが御国に入れられ時には、私を思い出してください」という祈りです。あなたのもとに引き上げてください。もっとあなたに近づきたい、もっとあなたを深く知りたいと願うことです。「苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。それにより、私はあなたのおきてを学びました。」と、この犯罪人のように、苦しみの中で引き上げられること、主のみそば近くに引き寄せられることなのです。
私たちも苦しみに会うととかくそこから救ってほしい、解放してほしいということしか考えられませんが、実はその苦しみこそ私たちが神のおきて学ぶ時として与えられるということを覚えていただきたいのです。そしてもう一人の犯罪人のように、「イエス様。あなたが御国に入れられるときには、私を思い出してください。」「ここから引き上げてください」と祈る者でありたいと思うのです。
Ⅲ.あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます(43)
最後に、この犯罪人の願いに対するイエスの答えを見て終わりたいと思います。43節をご覧ください。「イエスは彼に言われた。「まことに、あなたに言います。あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます。」」
これは、イエスが十字架の上で発せられた七つのことばの第二番目のことばです。「まことに、あなたに言います。あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます。」
「今日」ということばに注目してください。「あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます。」「いつか」「そのうちに」ではなく「今日」です。イエスを信じたその日に、もうパラダイスです。この「パラダイス」ということばは元々ペルシャ語から来たことばですが、その原意は、柵によって囲まれた園、および庭です。旧約聖書の中にもよく使われていますが、そこでは「園」と訳されています。でもそれはただの園ではなく天の園、神の国のこと、天の楽園のことを指しています。それが天国というところです。実際に天国は園のようなところです。そこにはいのちの木が生えていて、いのちの水の川が流れています。早く行ってみたいですね。まさに楽園です。ですからイエスが「あなたは今日、わたしとともにパラダイスにいます」という時、それはこの天の園、神の国のことを指して言われたのです。「今日、わたしとともにパラダイスにいます。」イエスを信じた今日、その瞬間、イエスは彼をこの天の園、神の国に伴ってくださると約束してくださったのです。彼は死の間際にすばらしい救いの約束を与えていただいたのです。
皆さん、救われるためには何かをしなければならないということはありません。救われるためには、ただイエスを信じればいいのです。イエスが自分の救いのためにすべてを成し遂げてくださったので、それら加えるものは何一つありません。もし救われるために何かをしなければならないとしたら、この犯罪人は救われなかったでしょう。だって十字架に磔にされてただ死ぬのを待っているだけの状態だったのですから。文字通り、手足が釘付けされている以上何もできないわけです。でも、イエスを信じた瞬間、信仰のゆえに、今日パラダイス、天国に行って、永遠にそこで過ごすという救いの約束を受けたのです。ただ神の恵みにより、キリスト・イエスの贖いによって。ただ神の恵みによって救われるのです。しかし、神の側では最大の犠牲を払ってくださったということを忘れてはなりません。
これがキリスト教の言うところの救いです。これ以外の宗教の説く救いというのは、全部何かをしなければならないというものです。信仰義認ではなく行為義認なのです。何らかの行いをしなければ救われないと言います。それは人間が作った宗教です。救われるためにはこうしなければならない、ああしなければならない、徳を積まなければならない、苦行をしなければならない、犠牲を払わなければならないと言うのです。でも、人が努力して自らを救うことができるならば、救い主は必要ありません。そのような人間の宗教で人が救われることはまずありません。せいぜいそれは気休め程度です。とんなに頑張っても、どんなに犠牲を払っても、死に打ち勝つことなどできないのです。そして、その頑張りによって自分を天国に入れるということなど絶対にできません。でも、イエスを信じるなら、あなたは救われます。信じたその瞬間にイエスとともにパラダイスにいるのです。何とすばらしい約束でしょうか。
イエスはこの約束を与えるにあたり、「まことに、あなたに言います。」と言われました。この「まことに」ということばは、原文でみると「アーメン」と記されています。イエスはご自身に救いを求めたその人に「まことに、あなたは今日わたしとともにパラダイスにいます。」と言われたのです。これはイエス様の感動が伝わってくることばです。
何がイエス様を十字架の苦しみの中にあっても「アーメン」と感動させたのでしょうか。それはこの犯罪人の一人が、自らの罪を認めてご自身に救いを求めたからです。生き直す時間がない絶望的な状態で、イエスを信じて救われたいと真実に願い求めたからです。ゴルゴタの丘に立てられた三本の十字架は、無意味に立てられたのではありません。イエス様をあざ笑う者の仲間になるのか、それともこの犯罪人のように自らの罪を認め、イエス様を信じるのかのどちらかです。イエスの救いを信じて、イエス様の救いに与りましょう。イエス様は、私たちを「アーメン」と言って救ってくださるお方なのです。
キッズ・バイブル・クラブ10月のご案内
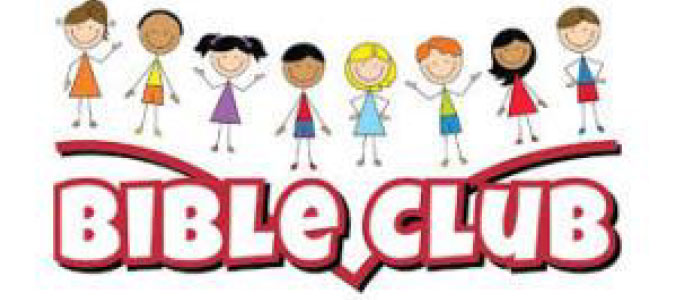
さくらチャーチでは10月第二、第四日曜日にキッズ・バイブル・クラブを開催しています。
キッズ・バイブル・クラブでは、幼児と小学生を対象に楽しく聖書を学びます。
どなたも自分の子どもがすくすくと成長することを願い、最善のものを与えたいと思っていますが、果たして、その最善のものを与えているでしょうか。
子どもにとっての最善のもの、それは物質的なものではなく、永遠につながる価値観です。
キッズ・バイブル・クラブではその大切な価値観を提供します。
キッズ・バイブル・クラブを通して、きっと自分が大切な存在であることを知り、生きる力と希望を見い出すことでしょう。
是非、お子様を参加させてください。心からお待ちしております。
なお、この学びは英語のクラスはありません。
あらかじめご了承ください。
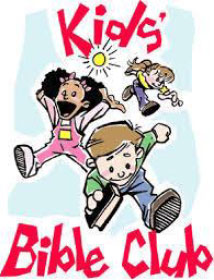
■とき:10月8日(日)、10月22日(日)
午後2時30分~3時30分
■会場:さくらコミュニティチャーチ
■対象:幼稚園児~小学生
■会費:無料
■お申込み:お子様のお名前と学年を明記してE-mailでお申込みください。
テーマ&主な内容
10/8(日)「井戸でイエスさまに出会った婦人」
*飲み物のクイズ
*クラッカーの大食
*水くみリレー などで楽しみましょう!
10/22(日)「イエスさまのところに連れていかれた女性」
*ボールなげ
*ボール捨てリレー
*ボールのダーツ など。
かんたんなおやつもつくるよ!
お問合せ:さくらコミュニティチャーチ
Tel:028-681-8317
E-mail:sakura39church@gmail.com

クリスマスチャペルコンサート
クリスマスチャペルコンサート
***フルートの調べが彩るクリスマス***
演奏者:紫園 香 Shion Kaori(フルーティスト・音楽伝道師)
フルート奏者の紫園 香さんが、素敵な演奏をしてくださいます!
【紫園 香 Shion Kaori プロフィール】
東京藝術大学附属高校、同大学、同大学院を各首席で卒業。川崎優、吉田雅夫、金昌国、M.モイーズ、A.マリオン、他各氏に師事。渡欧、モイーズ・マスターコース修了。
声楽を三林輝夫(二期会理事)に師事。第7回「万里の長城杯」国際コンクール他入賞多数。NHK洋楽オーディション入選。
NHKFM・TV出演多数。外務省招聘等により世界20ヶ国でリサイタル。ジュネーヴ国際芸術祭をはじめ国際音楽祭招聘多数。天皇に招聘され皇居にて御前演奏。東京文化会館・サントリーホールを始め国内主要ホールのリサイタルは常に高い評価を得ている。チャペルコンサート開催は世界2000ヶ所に及ぶ。
その多彩な活動はNHKFM・TVをはじめ、韓国CGN-TV、PBA-TV「ライフライン」、TV「ハーベストタイム」、FEBCラジオ、クリスチャン新聞、「百万人の福音」、「Manna」など、各番組・雑誌で大きく報じられ、音楽と信仰によって世界中に愛と平和を伝えている。現在、日本クラシックコンクール審査員。ムラマツ・フルート・レッスンセンター講師、ユーオーディア・アカデミー講師。いのちのことば社セミナー講師。ケニア「コイノニア教育センター」特別講師。日本バプテスト連盟東京バプテスト神学校教会音楽科講師。SIONの風プレイズ・ミニストリーズ主宰。キリスト品川教会音楽伝道師。10枚のオリジナルCD、曲集「Bless you」、著書「愛の風がきこえる」を発売中。2017年夏、11枚目「ビタミン・フルート」(いのちのことば社)発売。
Program
・すべて新たに(柳瀬佐和子)
・やすけさは川のごとく(Ph.P.ブリス)
・やさしき鳥たち(リヴィエ)
・ソナタト長調BWV525(J.S.バッハ)
・ロシアの謝肉祭(チアルディ)
・ クリスマス・メドレー
他
※曲目は変更になる場合があります。予めご了承ください。
開催日時:2017年12月9日(土)
開演:14:00(開場:13:30)
さくらコミュニティチャーチにて開催!
お問合せ:さくらコミュニティチャーチ
028-681-8317/sakura39church.gmail.com

フルート奏者の紫園 香さんのフルートコンサートです!
わかりやすい聖書の学び バイブルカフェのご案内
【わかりやすい聖書の学び バイブルカフェのご案内】
永遠のベストセラーである聖書を一緒に学んでみませんか?
アメリカ第16代大統領アブラハム・リンカーンは、「聖書は、神が人間に賜った最もすばらしい賜物である。人間の幸福にとって望ましいものはすべて聖書の中に含まれている。」と言いました。あなたもこのすばらしい聖書を一緒に学んでみませんか。初めて聖書を読まれる方、聖書を開いてみたけれども難しくてわからないという方にとって最適です。長年聖書を教えてきた経験豊かな牧師が、わかりやすく聖書をひもときます。お茶を囲みながらのリラックスした学びです。どなたもお気軽にお越しください。
講 師:大橋富男(牧師、実践神学博士)
開催日:毎月 第2,第4 水曜日
時 間:午前10時30分~12時00分
場 所:さくらコミュニティチャーチ(さくら市総合公園プール前)
参加費:無料
聖書は教会に用意してあります。
お気軽にお問い合わせください!
さくらコミュニティチャーチ
Tel.028-681-8317
Eメール sakura39church@gmail.com

バイブルカフェのご案内


